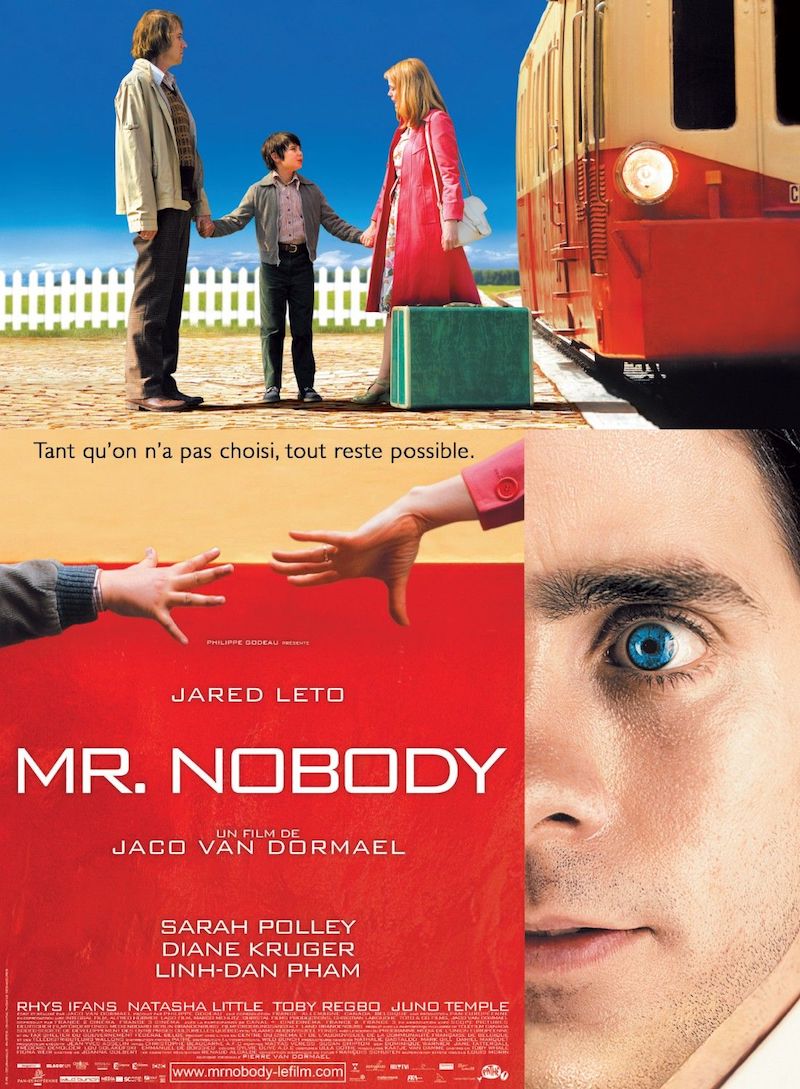石川ひまわりキッズシアター公演「私たちの空」が終了しました。
このなかで演じられる3つの短編それぞれについてエッセイを書く、ってのをやろうと思ってたんですが、2つめまでしか書いてまてーん。。。
なもんで、もう1個をちゃんとアップしようと書いてたら、いつのまにか演劇論の話になっちゃったんで、そっちを載せます。
「私たちの空」の第3部「私たちの命」についてのエッセイは、また後ほど書きます。ちゃんと書きます。べつに誰も望んでなかろうが、私自身が書かなくちゃならないと思っているのです。
ってわけで、演劇論の話です。

(琉球新報の「りゅうPON!」の1面にデカデカと掲載されました!)
演劇作品というのは、人工物である。まぎれもなく「作り物」である。自然の産物ではない。そこには製作者の意図や思想が意識的にしろ無意識的にしろ書き込まれている。
脚本を書く、という行為は、ある種の全能感を書き手にもたらしてしまう危険性がある。戯曲の中には、そこ(舞台上)がどんな場所で、どんな人物が登場して、どんな出来事が起こるのかが書き込まれる。
つまりそれらを決定する権利は脚本家に属している。脚本家が紙の上に書き付けた言葉によって、その作品世界は構成される。
脚本家が脚本を書くことに専念するのなら、その「全能感」も無害なものだ。
でも、舞台の脚本を書いた者がそのまま演出もする、というのがパターンとして多いような気がする。となると、いよいよ怪しげな香りが強まってくる。
どういうことかっていうと、つまりですね、その演劇作品が実際に上演された時、そこに現れるのが単に脚本を舞台上に転写したものになってしまう恐れがあるっていうことです。
言い方を変えると、脚本に書かれた言葉を忠実に再現しようとしてしまう可能性があるっていうことです。
言葉には〈音〉と〈意味〉という2つの側面がある。
たとえば「チョコ」という単語は、「チ」と「ョ」と「コ」という〈音〉の連なりですが、それは「茶色くて甘くて口に入れたら溶けてしまうお菓子」というような〈意味〉を表します。
本来この〈音〉と〈意味〉がセットになって一つの単語が成り立っています。
でも〈意味〉は、文脈によって用途が変わったり、ズレたり、膨らんだり、フットワークの軽いものでもあります。
演劇をつくる上では、この〈意味〉の「フットワークの軽さ」こそが、その作品世界を豊かにする鍵であるのだと思います。逆にいえば、〈音〉と〈意味〉がべったりと接着してしまった言葉では、複雑で豊かな世界は表現できないのだと思うのです。
となると、脚本には〈音〉を書き込むべきだと、わたしは思うようになりました。脚本の上では、〈意味〉によって言葉が連動するのではなく、〈音〉の流れを書き留める。脚本とはそうあるべきだ、そのように書くべきだと、特にこの「私たちの空」をつくっている最中は考えていました。
脚本に記された〈音〉を、役者は発します。その発声の仕方によって、そのときの姿勢によって、表情によって、つまり「音色」によって、〈意味〉は変化する。
それから、〈音〉は、役者が発する台詞のことだけを言うのではない。小道具や照明も(もちろん音楽も)ぜんぶ〈音〉だ。それらの使い方=「音色」によって、〈意味〉はどんどん増幅したりズレたりする。
脚本に記されている〈音〉を多様な「音色」によって奏でることで、豊かな〈意味〉が出現する。
いや、というよりも「捏造する」といった方が近い。脚本の〈音〉から〈意味〉を「捏造」する、それが「演出」をするということだ。
演出家が豊かな「捏造」をするためには、脚本とちゃんと距離を取る必要があるのだと思う。
「脚本家」が「演出家」を兼ねる場合、「演出家の私」は、「脚本家の私」の意図をどうしても汲んでしまう。そのことを避けるのはとても難しい。だからわたしはずっと、「演出」がわからなかった。どうやってやるべきなのか、自分が施す演出にまったくもって自信が持てなかった。いつまでたっても「脚本家」としての自分にお伺いをたてるようにして演出をしていた。
でも、この「私たちの空」をつくっているとき、ふと、「あぁ、そうか。」と思ったのです。


(当日は、約500人の方がお越しくださいました)
「私たちの空」は、役者として出演するのは全員小学生6年生の女の子。「大人」ではないし、訓練をしてきた「女優」でもない。いわば、「未熟」な存在です。
「未熟な身体」と「未熟な声」をもつ「未熟な役者」。その「未熟さ」は、ある意味では圧倒的な「強さ」を持っています。
どういうことかというと、「大人」や熟練の「女優」では、「未熟さ」を表現することがとても難しい、ということです。
なぜなら、「大人」や「女優」は、「未熟さ」を脱ぎ捨てることによって到達する場所だからです。
「未熟な身体」や「未熟な声」をもった存在に対して、「大人」や「女優」は、「未熟さ」においては勝ち目がありません。小さくなった服を無理して着ることは見苦しいので、それを簡単に着脱できてしまう人に着せよう、というようなことです。
で、「あぁ、そうか。」ってのは、この強度のある「未熟さ」に、脚本は「負け」てしまえばいいんだ、というふうに思ったってことです。
明確なイメージを設定して演じる少女たちにそこに合わせてもらう、そのイメージに沿うように指導する、というのではないってことです。
そうじゃなくて、「未熟さ」に負けて、その「未熟さ」をより瑞々しく表現できるような、そういった脚本にしたらいいんだ、と思ったのです。
そして、脚本が「負ける」ことを目指しはじめたとき、「演出」という方法も輪郭がクリアになってきました。
この作品においては、少女たちの「未熟さ」の強度を高めることで、劇作品として強いものになるのだと思えました。
演出は、脚本家の意向を慮るのではなく、脚本が「負け」を認めたその対象を思えばいいのだ。そう思えたら、なんかいろんなアイデアが浮かんできたのです。
だから今回の演出では、プロジェクターで映像を投影したり、音楽をガンガン使ったり、結構やりたい放題しました。やりすぎか?ってくらいに。
でも、手応えはあった。しかも、その手応えは、決して空っぽのものじゃないと思えました。その理由は、見にきてくれた人たちが、口々にコメントをくれたその内容にありました。
「子どもの可能性って改めてすごいね!! 何でもない会話なんて、しにリアルだし!」
「子ども達がやるから、より考えさせられた」
これらのコメントをもらったとき、「負ける」という方法論の可能性を感じました。
やろうとしていたこととお客さんの反応がこれほどバチっと合ったことは、いままで演劇をやってきて体験したことがなかったからです。
正直のところ、劇が始まる前は多くの人が、「学芸会の延長」くらいのイメージを持っていたんじゃないかと思います。
わたしはそのイメージを覆したかったし、小学生にしかできない、子どもがやるからこそ意味のある、強度のある、そんな作品にしたかった。
そしてそれは、これらのコメントを見る限りある程度は達成できたのかなと思います。
もちろん、もっと改良できるところ、強度を高められるところはたくさんあります。でも、この方向性はイケる!という確信を得たのは大きい。これは非常に自信になりました。
ちなみに、この「負ける」という表現は、建築家の隈研吾さんの「負ける建築」というテーゼから勝手に拝借したものです。いっちゃうと「パクリ」なんですが、まあ、別にいいじゃないですか、今回ばかりは。
というわけで、今後とも「負ける演劇」をしっかりとめざしていきたいと思います。

(この子たちの可能性に「負けた」のです)