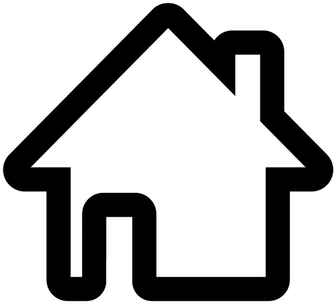未完成で荒削りな主人公が、個性あふれるチームメイトや強力なライバルと切磋琢磨していくなかで、次第にその潜在能力を開花させていき、ついには強大な敵を打ち破る。
そのような「成長譚」が、野球に限らずスポーツ漫画の王道パターンであり、その話型は、読者に予めその展開自体をわかられていたとしても、興奮と熱狂を産出させる。
急速な成長を遂げる主人公は、いわば読者の分身であり、読者は彼(彼女)に、無意識のうちに勝利を義務付ける。私(読者)は主人公に半身を付託し、私の代わりに主人公に勝利(成長)をしてもらう。
これは単に「主人公に感情移入した」ということではなく、私たちが持つある性質についての話である。
たとえばHDDがテレビに接続できるようになって、見たいテレビ番組を保存することが簡単になった。以前のようにVHSへの録画しか方法がなかったとき、それは物質的に有限なメディアであり、なんでもかんでも録画する、ということはできなかった。
でもいまは、なんでもホイホイとボタン一つで記録に残すことができる。HDDにももちろん容量に限りはあるが、それは物質的な目に見える形ではない。それに、これまたボタン一つでサクサクと消去することもできる。
そういう便利な機能を使って私たちは、以前より多くの番組を録画するようになった。ただ、それらの番組を再生する機会は、増えたと言えるだろうか? 録画したまま、視聴しないまま保存されている番組。あるいは、一度も再生することなく消去した番組。そういったものは、どんどんどんどん増えている。
私たちは、容量を拡張し続けるメディアに、記録を請け負ってもらうと同時に、「視聴」までやってもらった気になっているのではないか。つまり、HDDに保存した時点で「すでに見た気」になっているのではないだろうか。
私たちは容量だけ食う録画番組のリストを眺めるだけで、満足できてしまう。そしてその番組を見ずに済むことで、浮いた時間を無為に過ごすことすらできてしまう。
このような「受動的」な態度さえ外部に委託できてしまう「相互受動性」を、私たちは所持している。
私自身が成長の快楽や勝利の美酒を浴びる可能性もあるはずなのに、私は、その私自身の「受動性」を主人公に譲りわたす。
彼(=主人公)が成長し勝利をする間に、私たちは、自分の部屋の掃除をしたり、お得意先を訪問したり、溜まったデスクワークを処理することができる。つまり、自らのプライベートや仕事をマイペースに過ごすことができる。私たちは、私たち自身が急激な成長をしたり勝利をしたりせずとも、主人公の快進撃を観察するだけで満足できる。それによってある種の「達成感」が、私自身にももたらされるのである。
この相互受動的な感性をど真ん中から撃ち抜くからこそ、スポーツ漫画の王道な展開を、読者は常に求め続けるようになる。
この「相互受動性」によってもたらされるのは、「達成感」のほかにもうひとつある。それは「感動」である。
ただし、読者(私)は、主人公の快進撃に興奮はしても、それ自体に「感動」をしているのではない。「感動」を享受するとき、その「受動性」を共有しているのは主人公ではなく「脇役」にである。
たとえば高校野球を題材にしたマンガ作品などには、ヒロイン的な存在として「女子マネージャー」が登場したりする。彼女は主人公に、私たち読者もうそうするように、「達成感」をもたらす受動性を委譲させている。しかし同時に彼女は、「感動」を感じる受動性は自らしっかりと握っているのである。どういうことか。
たとえば彼女は、主人公たち(プレーヤー)が心・技・体それからチームワークを高めるために、献身的に、あるいは時に積極的に介入しながら、自らの身体・精神・時間をそこに投げ出している。
ただ、彼女の仕事はプレーヤーのマネジメントであり、彼女自身が実際にグラウンドで汗を流しているわけではない。その意味で、彼女が得た「達成感」がどれほど大きなものであったとしても、それは間接的なものに止まる。
とはいえ、彼女は実際にプレーはしないが、チームの勝利のために労働をしていることは確かであり、だからこそ、勝利による「感動」を、彼女は直接的に授かることができる。
「感動」とは、本質的に受動的なものである。他者・外部から到来するなにかに、私たちは心を打たれる。だから、グラウンドの上で戦っているプレーヤーたちは、構造的に「感動」することはできない。「感動」は、その試合、そのプレーを見る側だけに与えられた特権なのである。
プレーヤー特有の「達成感」と傍観者特有の「感動」を同時に享受できる位置に読者は立っていて、その読者に、同時にしかもほぼ確実に「達成感」と「感動」を送信できるコンテンツとして、あらゆるスポーツ漫画が「王道」な話型を踏襲してきた。
そういった意味で『ダイヤのA(エース)』は、成長譚という王道パターンを踏襲したマンガ作品だといえる。
主人公の沢村栄純は、高校野球の名門・青道高校に所属する1年生投手である。
荒削りながら、先輩や同級生たちと競い合い、高め合い、甲子園を目指す、そういった物語である。
物語は、沢村の中学時代からはじまる。
沢村は中学時代、弱小野球部に所属していた。中学校最後の試合、最後の投球。キャッチャーが捕ることもできない大暴投をして、結果的にサヨナラ負けとなるが、その最後の「大暴投」を見初められ、彼は青道高校野球部にスカウトされることになった。
ただ、スカウトされた彼は、入学を渋る。彼はチームメイトに「このメンバーで甲子園に行こう!」と強く宣言していたから、その彼自身が野球の名門校である青道高校に入学することは、チームメイトを裏切ることになってしまう。その葛藤が、単行本の1巻のはじめで描かれている。
沢村とチームメイトとの対比が、読者自身のアイデンティティの揺らぎそのものである。
つまり、沢村という、強豪校に入学して甲子園で旋風を巻き起こすかもしれないという「理想(理想自我)」と、自らの能力や周囲との差を感じ取り、自らにブレーキをかけざるを得ないチームメイトという「現実(超自我)」。
この対置によって、読者は、自身の中で分裂してしまっている自我を、沢村とチームメイトそれぞれに投影させることができる。
そして沢村は、チームメイトから祝福して送り出されるようなカタチで、青道高校への入学を決める。
その時点で、沢村は、チームメイトの受動性(勝利による達成感を浴びる権利)を引き受けることになる。そして残されたチームメイトたちは、沢村という人間の形成に関与した「影の功労者」としての地位を得て、「感動」を受信する立場に自らを落ち着ける。
このようなセットアップを物語冒頭で完了させた時点で、『ダイヤのA(エース)』は、読者を心置きなく「達成感」や「感動」へと導く通路を開拓させることに成功したのである。
ところで、沢村が青道高校に入学するきっかけとなったのは、大暴投の際に彼が放った「ムービングボール」である。「ムービングボール」とは、簡単にいうと「クセ球」のことで、ストレートと同じ速さながら打者の手元で微妙に変化し、バッターがうまく捉えることが難しい球種だといえる。
沢村は、生まれ持った身体性(関節の柔らかさなど)や、そのクセを矯正されないような野球環境であったことも手伝って、無意識のうちにこの「クセ球」を駆使する稀有な投手になっていた。この「ムービングボール」こそが、沢村の個性であり、長所であり、唯一の拠り所であった。
ただ、この「ムービングボール」は、それを投じる本人自体がその軌道をコントロールできない、というところに特徴がある。どのような変化をするのか予測することは不可能で、ややもすると何の変化も起きないただの棒球(特徴のないボール)になってしまう危険性もある。
彼が青道高校でチームメイトとなる部員たちは、皆はっきりとした「強み・個性」を持つ選手たちだ。同じピッチャーの降谷は「豪速球」、内野の小湊は「バットコントロール」、女房役となる御幸センパイはキャッチャーとしての天才的な「頭脳」。
それに比べて沢村の「ムービングボール」は、いまいちハッキリしない。このことは、なにを表しているのだろうか。
さきほど、沢村は読者自身の「理想(理想自我)」の投影である、と書いた。
沢村という存在は、弱小野球部という決して恵まれたとはいえない環境で育まれ、それゆえにその環境でしか獲得され得ない希少的な能力を授かった(はずの)者である。際立った才能を持たずとも、徹底的に鍛えられた技術を持たずとも、彼自身に本来的に備わっている「なにか(個性)」が、いわゆる野球エリートとの階級差などの閉塞を打ち破る突破口となる(はず)。
この部分の「沢村」を、読者自身としての「私」に置き換えても、この文章はそのまま成立する。
つまりこの「沢村」という主人公の設定は、自分が何者であるか曖昧でありながら、でも何者かでありたいと願う私たちの「アイデンティティの危機」をそのまま記号化したキャラクターなのである。
だから読者である私たちは、沢村に「成長」してもらわないと困る。「勝利」してもらわないと困る。なぜなら、沢村の「停滞」はそのまま私の「停滞」を意味し、彼の「敗北」は私の「敗北」であるから。
これにより、私たちはより沢村への同一化(投影)を強める。彼の一挙手一投足に一喜一憂する。読者から主人公への「転移」が、ここでは強化されることとなるのである。
この作品の中ではよく、沢村がひとり、重いタイヤを引いてダッシュをしているシーンが描かれる。夜遅く、グラウンドには沢村以外に誰もいない。そんななかでの自主的なトレーニングを行いながら、彼はエースになる自らの姿を思い描いている。
彼の人知れぬ努力や心意気を、知っているのは、世界のなかで読者しかいない。読者だけが、彼の姿を観察している。その事実は、読者自身に不安を抱かせるものである。沢村(=読者)の頑張りを、誰かに見ていてもらいたい、認めてもらいたい。でも、周囲を見回しても、私以外にその頑張りを評価してくれる者はいない。そんなときに私たち読者は能動的に、受動的な存在を探すようになる。
そうしていると、実は沢村の自主トレーニングを遠くで見つめている人物がいる、というコマが挿入される。それは多くの場合、「あいつもよくやるなぁ」「悔しがってんだなぁ」などというつぶやきを交わしながら、視線を沢村に奪われている先輩たちの姿である。
そこで私たちはようやく不安を解消することができる。沢村の姿を観察するという受動性を引き受けてくれる存在(先輩たち)が見つかったので、それを全部彼らに任せてしまって、安心してまたストーリーにのめり込むことができるのである。
これらのようなやり方で、『ダイヤのA(エース)』は、私たちのアイデンティティに揺さぶりをかける。そしてスポーツ漫画の「王道」的なやり方で、主人公の成長や勝利を、私たち読者に追体験させる。そして私たちはその流れに自らを重ね合わせ、自らのアイデンティティを再確立しようと試みる。
そう考えると、「王道」的作品というのは、もはやコンテンツというよりも、読者の自我の「容れ物」として考えることができるのではないか。自らの理想や感情をそこに自由に挿入することができるように最適化されたものとして、「王道」的パターンを再定義することができるのではないだろうか。
王道的スポーツ漫画の生み出す興奮や熱狂は、「アイデンティティの確立/危機」という、すべての人に共通するテーマを提示することによって産出されているのであり、だからこそ幅広い読者を獲得することができるのである。