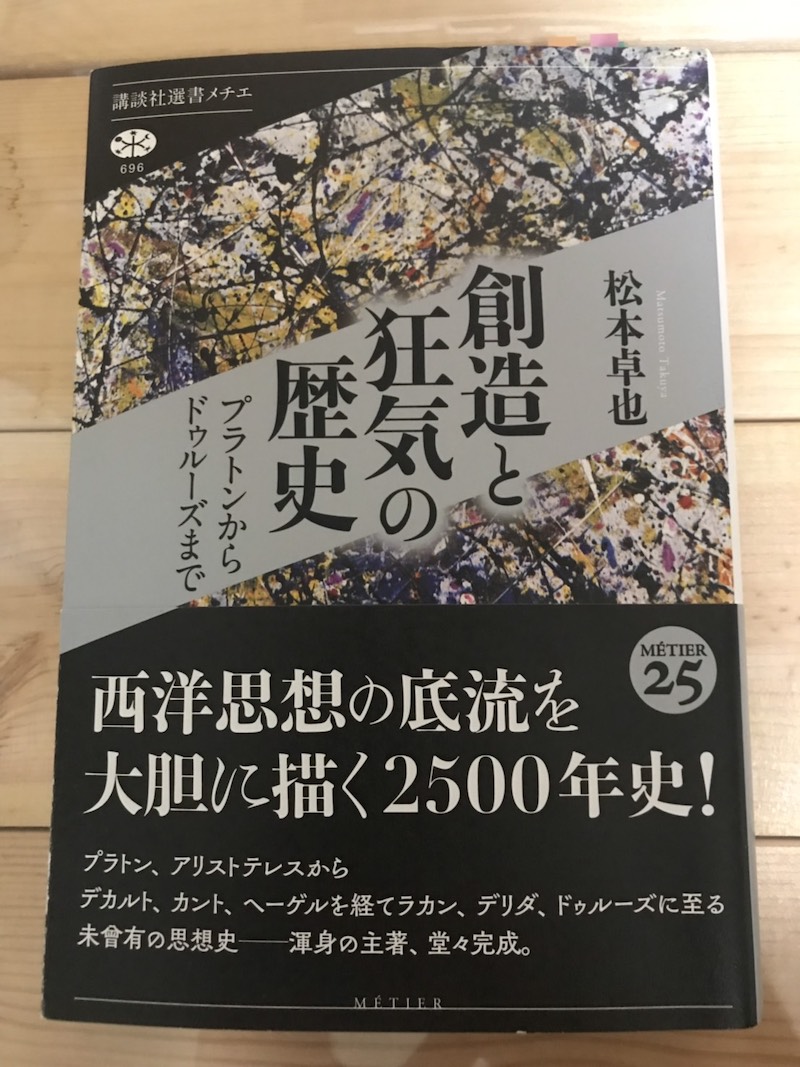『レ・ミゼラブル』(ダヴィデ・ドーロ演出)

名前は知ってるけど観たことないものベスト10には入るんじゃなかろうかという作品、レ・ミゼラブル。通称「レミゼ」。
映画は観た気がするのだけど、正直あまり覚えていなかった。なので、知ってるけど観てない、にカウントしてください(誰が集計してるの?)。
この「レミゼ」が、今年のりっかりっか*フェスタで上演されていたわけです。それを観たお、というのが、いまからここに書くことだお。
さて、この「レミゼ」。本来はめっちゃ超大作なわけで。それを女性2人で、70分の時間で上演ってことでした。
って、それどーやってやんの?っていう話なわけで。そもそも。
この作品を演出したのは、ダヴィデ・ドーロさんというイタリア人の方(らしい)。よーやるな兄ちゃん。てな感じでよー。
パン1枚盗んだ罪で19年間投獄されたジャン・バルジャン。そのバルジャンを追う警官ジャベール。その他諸々の登場人物たち。ぜんぶ説明するべきでしょうか。ちょっと面倒臭い。もし必要だと思ったら後で追加で書き込みます(もしこの文章がそのまま掲載されていた場合は、「あー、あいつサボったなー」って思っていただいて結構です)。
ってさ、こうやって書いていますけども、このブロックだけですでに150字以上を費やしておりますけれども、あらすじや登場人物の詳細を書くかどうか迷ってますみたいなこと言って渋ってるくせに、本筋に一切関係のないどうでもいいことはここに吐露するみたいなことを延々やっているといういまのこの現状。
そういうとこやぞお前!って、わたしはワタシにツッコミを入れる。しゃんとせい!
でもね、そうは言いますけど、原作自体が長大な(以下略)。
というしつこい記述をどうかお許しください。でもね、ジャベールはそれ以上にしつこいんです。
しかも、こういう薄っぺらいしつこさじゃなくて、おもーーい上にしつこーーい。
うむ。どう書いても、重さが伝わらない。。。。
とにかく、悪を憎むジャベールは、パン1枚を盗んで投獄され出所後も軽犯罪を起こして逃亡しまくっているバルジャンを、執拗に、これはもう本当に病的に、狂ったように追いかけます。取り憑かれています。スーパーウルトラ厳格原理主義者です、彼。
19年ぶりに娑婆に出てきたバルジャンは、助けてくれた神父様から銀の皿などを盗み、街中の子どもの金を盗み、なーにやってんだよお前は!っていう、普通にダメなやつです。ほんと。
でも、この作品は、その「ダメ」な男を描くのです。
なぜ彼は「ダメ」になったのか。なぜ「ダメ」にならざるを得なかったのか。そこを直視しようとします。
それはやっぱり「貧困」だからです。あるいはそれから派生する「格差」。「貧困」が、彼から、生きていくうえでの選択肢を阻害したのです。
パンの1つもお金を払って買うことができない。失業によってそのような境遇に追い込まれてしまった人を、あなたは断罪できるのか、という問いがここで突きつけられます。
そして、ジャベールは怯まず断罪します。罪は罪だと。悪は悪だと。
このときに、観客のわたしたちは気付かされるのです。これほど執拗なまでに悪を裁こうとするジャベール自身が「なにか」を抱えているんじゃないかと。バルジャンを追いかけているジャベール自身が「なにか」に追われているんじゃないかと。
それを振り払いたくて、彼は「正義」に縋っている。「正義」を振りかざしている瞬間だけは、ジャベールは「なにか」から遠くにいられる。言い換えるなら、ジャベールは「なにか」によって、「正義」へと追いやられているのではないだろうか。
そういうふうに振り返ってみると、バルジャンだけではなくジャベールも、実は「逃亡者」であると見ることができる。
「レミゼ」で描かれる、フランス革命後の人々を映したこの作品を、演出のドーロはなぜ創作しようとしたのか。
「りっかりっか*フェスタ」での作品紹介のページにはこう記載があった(HP)。
人々の想いと願いが、時代を超えて私たちの心に訴えかける。必見の名作「レ・ミゼラブル」
2016年のフェスタで創作され、好評を博した作品。
ヴィクトル・ユーゴーの大作「レ・ミゼラブル」を、2人の俳優がオブジェクトシアターで綴る挑戦作。
権力や社会に抗い、生きることを諦めない人々の想い、愛、そして命を、独自の演出で描き出します。
「レ・ミゼラブル」の中に生きる生々しい人間たちの姿は、ダヴィデ・ドーロ(コンパーニア・ロディージオ/イタリア)の新たな解釈と演出により、現代を生きる観客の心に強く訴えかけることでしょう。
こういう紹介文があるなら最初の方で載せておけよ、と思った方。
ええ。あなたは正しい。
わたし自身も、冒頭の方(あらすじを書き渋っていたところ)を削ってここを書けばいいじゃん、なんて思ってる。
でも、そうはしないっていう。なぜか。うーん。だって、ちょっと面倒ですし。。。
閑話休題。
紹介文は、「現代を生きる観客の心に強く訴えかけることでしょう」と締めくくられる。
つまりこの作品は「現代」にむけて、「現代」を生きている私たちにむけて創作されたものだということだ。
ある意味、当然の話です。なんらかの必然性があるから、古典作品は現代においても上演されるわけです。
じゃあその「必然性」とやらは? そのひとつはさきほども出てきたように、「貧困」であることといえるのではないでしょうか。
「貧困」あるいは「格差」という問題は、現代になってもまだまだなくなっていません。
わたしたちの住む社会は、貧しさに喘ぐ人たちを、あたかも「『怠惰』という罪」を犯したかのように扱ってしまいます。
貧しいのは、働かないから、勉強をしないから、そこから抜け出す努力をしないから。そういって「自己責任」の一言でスパッと斬って、楽して暮らそうとする罪人、みたいなカテゴリーに押し込めてしまう。
たしかに、生活保護制度などで不正受給をする人がいるという問題も一部にはあるでしょう。
でも、決して生活保護世帯がみんなそういうわけじゃない。というより、そういう人はほんの一握りなわけでして。
貧困世帯が「抜け出す努力」をしてないわけじゃなくて、そもそも「抜け出す努力」の前に食べるのに必死なわけです。
今日を生き延びるために目の前の「パン1枚」を手に入れることでいっぱいいっぱいなんです。
そういった構造的な問題を是正するのが社会にとっての重要課題であるわけで、その問題を個人にすべて丸投げするのは、社会の機能が弱体化しているといえます。
それともうひとつ、わたしたちの社会は貧困者に対して、「理想的な姿」を求めてしまいがちな気がします。
その姿というのは、清貧とでもいうべきか、必死に健気に一生懸命に脇目も振らずただただ頑張って目の前の生活に勤しむ、というような姿勢。
乱暴な言い方をすると、貧乏人は贅沢をするな、ということです。そんなふうに割に合わない消費をするから貧乏なのだ、という見方のことです。
自己責任を徹底し清貧なふるまいをする、そういう「自立的」で「自律的」な貧困者ってさ。。。そうなるのが構造的に排除されてるから貧困なんでしょ?なんてわたしなんかは思うのですがどうなんでしょう。
そういったことを少しずつ解消してくために社会の成員がどうふるまうか。そこでその社会の成熟度が問われるわけです。
金銭や食料に少し余裕のある人はなんらかの寄付をするかもしれないし、時間に余裕がある人は社会運動(デモ)などに参加するかもしれない。
いろいろな仕方で社会をよりよい方向に、より多くの人が生きやすい社会に変えていく働きかけができるはずです。
レミゼのなかでも、バルジャンに施しをする神父様や、デモを行う若者たちも登場します。社会成員のそのようなふるまいは、ずっと昔からあり続ける、あり続けるべき姿なのです。
ところで、わたしはいま理想論を述べています。ええ。お花畑だと言われるかもしれません。
でも、それを言う人がいないとダメだと思うんです。
演出家のドーロさんがやっているのも、ある意味で「お花畑」です。でも、それが大事なのです。
演劇でわざわざ「お花畑」をやる。そのことの意義を、わたしたちはもっと考えたほうがいい。
たしかに、その上演がどんな豊かなものであっても、貧困に喘ぐ人にとってはパン1枚のほうが重要です。その現実に演劇は打ち勝てません。
でも、さきほども述べたように、貧困などの構造的問題を是正するのは社会全体の課題であり、その「社会」に対する働きかけとして捉えるならば、演劇で「お花畑」をやる意義は大いにあります。
観客を劇場という「非日常」に誘い「お花畑」を上演するのは、観終わった後に「日常」に戻り「現実」に直面するためです。
一度劇場を潜って出てきた後で対峙する「日常」や「現実」は、それまでとは少し違って見えるようになります。その経験を、その感覚を、多くの人が抱き、「社会」の側が少しずつ変化していく。
今回の例でいえば、「貧困」や「格差」というものに対する見方が少しだけでも変化するかもしれない。
それが「お花畑」を上演する意義なのです。
では、今回のレミゼでは、どんな「お花畑」がつくられ、あるいはどのようにつくられていたのでしょうか。
今回のドーロ演出では、まず特徴的だったのは美術セット。舞台の中央に直径1.5メートルくらいの大きさで円状に黒い砂が盛られ、それ以外はなにもない。舞台後方に黒い布で覆われたなにかがあるのだけれど、はじめはそれがなんなのかは見えません。
物語が中盤を過ぎたあたりから、盛られた黒砂の意図が明らかになります。それまでは二人の女優が縦横無尽に駆け回りながら演じられていた舞台空間がぐっと縮小して、砂の上に小さな箱型の家や建物が置かれ、やがてそれがバルジャンが形成した街(工場を建て街が活性化し、その後市長となった)であることがわかります。
そのとき気付くのは、バルジャンのつくった街と上演されている空間(演出の意図/テーマ)とがシンクロしていること。どちらも自分たちの手で、自分たちの出来る範囲で、「お花畑をつくろう」という意志が示されているのだと思われます。次第にふたりの女優はその生身の身体ではなく、砂の上で人形を動かしながらセリフを発するようになる(=オブジェクトシアター)ことからも、そのことは言えるのではないでしょうか。
だから、まず自分たちで、自分たちの出来る範囲で生活を作っていく、という姿。それが「お花畑」のひとつです。
ただ、これは「自己責任」論とは別だと強く主張したい。限られた範囲の中でベターな方を選び取っていこうという意志であり、できるならば選択肢は多い方がいい。
問題は選択肢がはじめから限定されていることなので、選択肢を広げるための施策が社会の側に求められているのである。
いまの時代は世界的に見ても緊縮政策がすすめられる傾向があり、福祉は削がれそれによってますます貧困者の生活が苦しくなっている。格差はなくなるどころか広まり、固定化する。
だから、ハンドメイドな範囲で生活を向上させようとする個人の側だけではなく、それをサポートしたりエンパワメントするような人材や制度(社会)の形成が必須なのだ。
中央の黒砂のなかだけに縮小していくバルジャンたちのいる世界。これは緊縮化が進む世界情勢の比喩として読み取ることもできよう。
ただし、ドーロが空間全体を使って「緊縮」を描くのではなく舞台中央だけでそれを描いたのには、はっきり意味があるとわたしは思う。
これは反転させると、黒砂の外に空間(空白)があるということ、つまりわたしたち観客(社会)に、その空白の存在と可能性を示しているのではないか。
わたしたちがその空白に立ち入り、黒砂の中になんらかの働きかけを行うことができるのではないかということ。その黒砂の範囲を広げていく余地がこれほど大きくあるのだということ。
それができる潜在的な力を、観客(社会)は秘めている。はじめは砂に埋もれていた小道具たちが次第に存在感を増してくるのも、そのメタファーと捉えることができる。
黒砂を広げていく社会的・政治的なアクション、それは作品の中でも描かれる革命ともリンクしている。
それはイデオロギー対立での転覆ではなく、生活の向上を求めるものだ。
緊縮政策などのように、「政治」に生活が食いつぶされてはならない。それが、彼が描こうとしたことだったんじゃないだろうか。
政治はイデオロギーのマウント合戦のためにあるのではなくて、生活のためにあらねばならない。
そういう意味でいえば、自らの生活をつくる、という行為は、完全に政治的な行為である。
この物語を感動的なものとしての消費にとどめることなく、「貧困」「格差」あるいは「緊縮」という現代的な問題に向き合う時のひとつの題材として提示する。これが「お花畑」を上演するということだ。
さて、ジャベールは、「なにか」から逃げていると書いた。なにから逃げていたのだろうか。
とりあえずこのテキストでの結論としては、貧困・格差・緊縮などの問題を抱える「現実」、というあたりだろうか。
数多の問題を含んだ現実から目を逸らし、他者を断罪する。その行為を取り憑かれたように執拗に行うことで分断は生まれ、貧困者の存在・立場・声がどんどん不可視化されていく。
物語の終盤、ジャベールは、バルジャンをひたすら追いかけ回してきた行為ひいては人生を問い、自ら命を絶つことになる。
彼は死ぬ間際、なにを見たのだろうか。「犯罪者」として追跡してきたバルジャンのような存在のその隙間から、なんらかのものを嗅ぎ取ったのだろうか。
わからないけれど、観客であるわたしたちは、わたしたち自身に問いかけてみると、それに近いものが、たぶん湧き出てくるんじゃないかと思う。