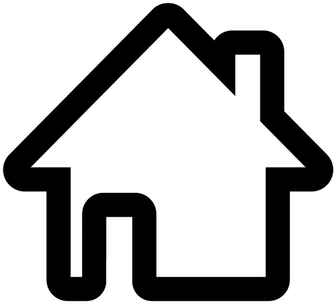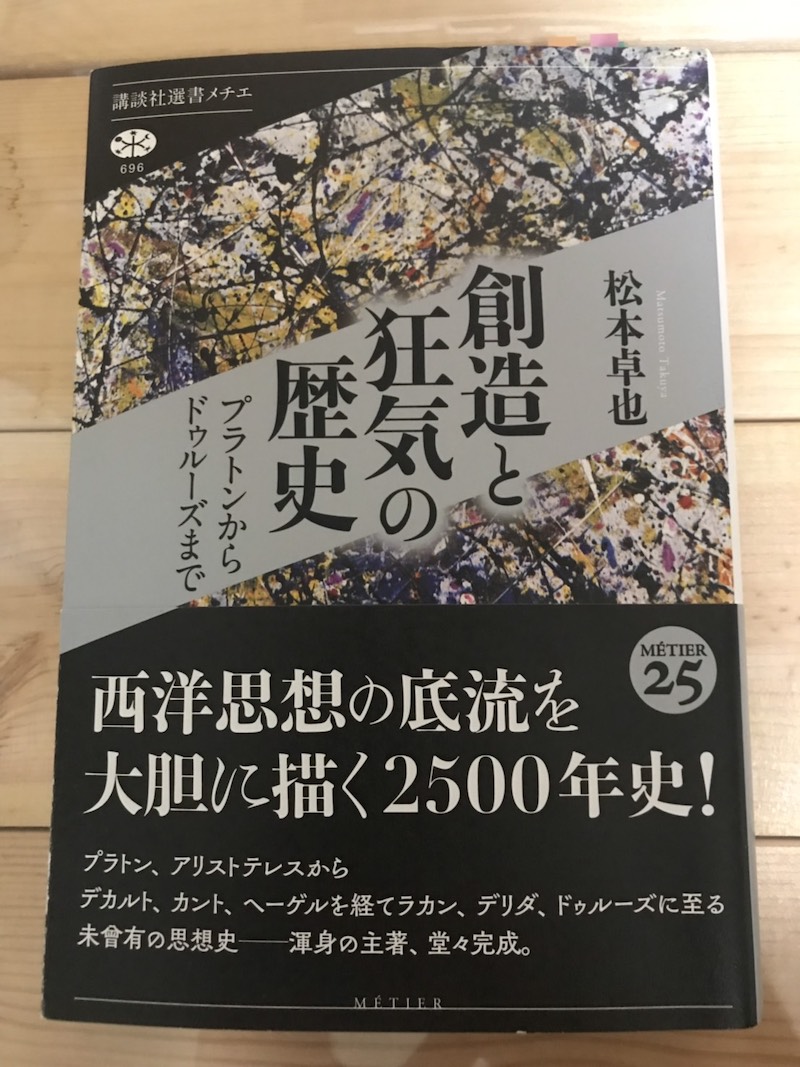
おもしろかったので、本の内容をまとめます。
精神科医である松本卓也さんの『創造と狂気の歴史』、副題は「プラトンからドゥルーズまで」。
一応、クリエイターの端くれとして細々と活動しているわたしですので、なにかしらヒントがあればいいなと。
でもそれよりも、松本さんはラカニアンでありながらドゥルージアンでもあり、最近はドゥルーズと自閉症スペクトラム(ASD)を結びつけて語るような活動をいろいろやっていて、それがめっちゃおもしろいので、だからこの本の最終章のドゥルーズの章を読みたくて買ったんです。
まあ端的にいうと、テーマは狂気(クレイジー)と創造(クリエイティヴ)の関係性が歴史的にどう捉えられてきたか、というものです。
古くは「神懸かり」とか「悪霊憑き」とかそういった人を「クリエイティヴ」と捉えていたのが、デカルト、カント、ヘーゲルあたりで人間が「近代的主体」となって、理性的な存在となって、狂気的なものは排除されます。
しかし排除されたはずの狂気は、理性的である近代的主体の「内部」に回帰する。そしてその内部に閉じ込めた狂気を発現させる人たちが出てきます。それが、統合失調症(分裂病)者でした。近代になって登場した統合失調症という病は、最終的にはそれを患うものの理性の解体に向かわせ、その引き換えに「真理」や「表象不可能なもの」を取り出すことができるのだとされました。
そんな統合失調症の最初期の病者で、かつ傑出した詩人でもあったのがヘルダーリン(ヘーゲルの親友)です。彼の作品および狂気性を批評した哲学者ハイデガーの論(「詩の否定神学」)が大きな影響力を持ち、ラカンやフーコーらフランスの思想家たちによって語られていきました。
その過程で、ヘルダーリンおよび統合失調症者の狂気=創造性が連れてくる「真理」や「深さ」が重要視されるようになり芸術作品と病との関係について研究する病跡学の分野において、「統合失調症中心主義」とでもいうべき特権化がなされるようになりました。そしてそれは統合失調症者を、狂気に落ち込むなかで真理を取り出す悲劇的な創造者として位置付けました(「悲劇主義的パラダイム」)。
その「統合失調症中心主義」と「悲劇主義的パラダイム」から逃れるように、狂気と創造との関係を考えていったのが、ドゥルーズでした。ドゥルーズは、ルイス・キャロルやレーモン・ルーセル、ルイス・ウルフソンなどの、言葉の表面的な使用にどこまでも興じようとする作家たちを重要視しました。統合失調症者が命を賭してまで取り出そうとする「深さ」とは裏腹に、キャロルらの作品はダジャレやアナグラムなどの言葉遊びから成る表面的で「浅い」ものでした。でもドゥルーズはその「浅さ」こそを評価したのです。
彼らは「言語の内部で一種の外国語を形成する」ようにして作品を書きました。すなわちすでにある既存の凡庸な言葉を神的な力を借りて外側から解体しようとするのではなく、むしろ既存の言葉をその内側からハッキングすることによって転覆させようとしました。
言語をハッキングすること、つまり言語をその慣習的な轍の外へ引きずり出すことが、現代において言語そのものを狂気させようという試みなのでした。
キャロル、ルーセル、ウルフソンらは、当時は統合失調症者としてみられていましたが、その特性等をみるに、いまでいう自閉症スペクトラム(ASD)だっただろうといわれています。実際に、現在いわれているASDの特性と彼らの作品内容との関連は多くみられます。
統合失調症が特権化されてきたのは、その存在が、あるいは患者のなかにある狂気が、絶対的な「他者」だと見なされたからです。翻って、ASDは、端的にいうと「他者」が存在しないのです。彼らは、予測不可能性や不確定性を避け、未知なものが存在しない計量的な世界に立てこもり「他者」を回避しようとする構造をもっています。
生まれ落ちたときから、一方的かつ強制的に与えられ、覚え込まされ、自分のあらゆる欲求をその言葉で表現するよう強いられる支配的な言語=母国語への参入をASD者は拒絶します。その母国語をハッキングしようと企てたのがキャロルたちのような作家でした。
彼らの作品は徹底的に表面的で浅いが、その表面上の言葉の操作にただただ依拠し続けることで、「他者」に侵入されることなしに深層とかかわることを可能にする“かもしれない”。そうドゥルーズは考えました。あくまでも“かもしれない”という偶然的なものですが、ドゥルーズはその偶然性に、創造の発展を賭けたのでした。
現代では、統合失調症自体が軽症化し、医学の進歩によって治癒や改善がなされる病となりました。それに伴い、病跡学における統合失調症中心主義もその遠心力を失いつつあります。そのような時代の流れのなかで、創造と狂気の関係性はどのように変化していくのか。
松本さんは、その可能性のひとつとしてASDの研究があるのではないか、と考えたのです。
わたしは昨年上演した作品について、ほとんど毎回わたしの作品を観劇してくれている友人から、「自閉っぽい」という言葉をもらいました。あのときは特にピンときてなかったのですが、この本を読み終えてみて、なんとなく腑に落ちた感じがしました。
べつにわたしは「狂気の作家」ではないし、徹底した言語使用に興じられるほどの忍耐力もありませんが、俗っぽいものを書く作家だと思っています。なので、もっともっと俗っぽく。そんなことを、この本を読み終えた今、思っているのでした。