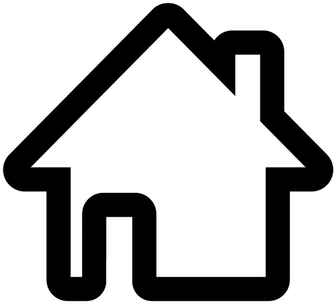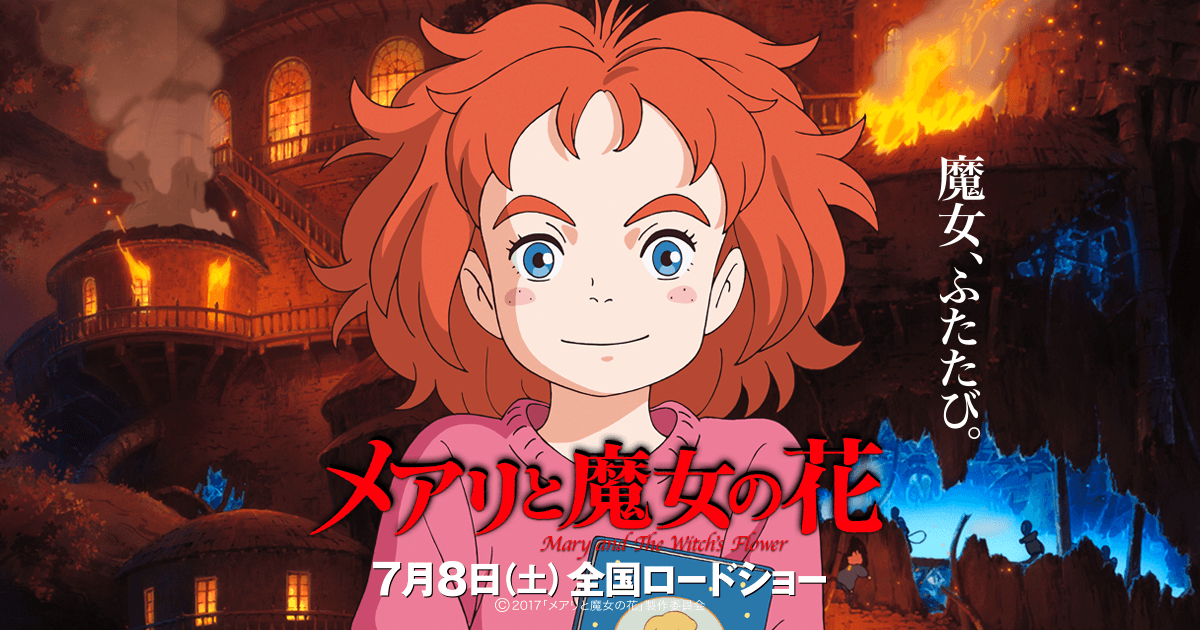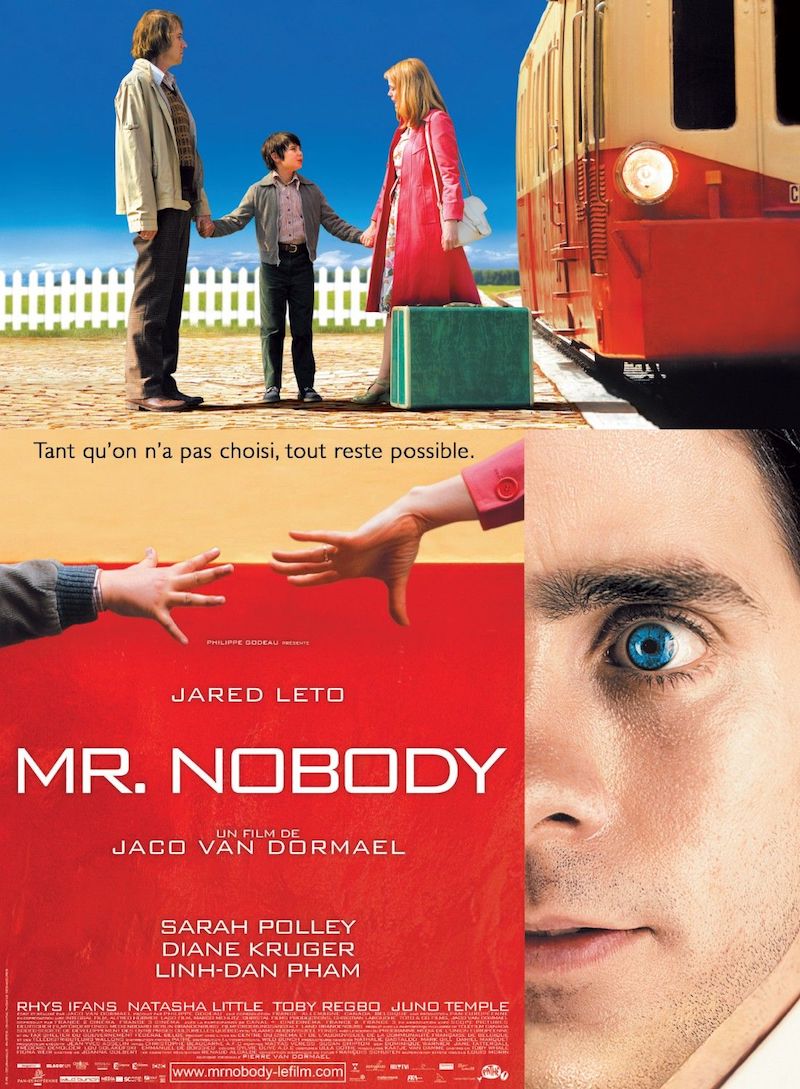『ミラクルシティコザ』、映画館で観てきた。
コザの街が大きなスクリーンに映し出された瞬間はなんともいえない感慨を抱いた。
よく県外での紹介のされ方にコザ=沖縄市みたいなのがあるけど、ローカルな感覚で言えば沖縄市とコザは必ずしもイコールではないし、わたしは沖縄市出身だけどコザ出身ではない。
と書くと地理的に詳しくない人は混乱してしまうかもしれないけど、ざっくり言うと沖縄市とはコザ市と美里村が合併してできた自治体で、わたしは美里村側の人間なのです。
だからなんだというわけですが、わたしはコザの街自体にアイデンティティやノスタルジーはあまり抱いていないと自覚していたにも関わらず、コザの街が映しだれたその映像に否応なく昂ってしまったのであります。
というわけで映画の感想を記すが、前もって断っておけば、わたしはこの映画はどちらかというと苦手だと感じたし、だからこれから書くこともその大半は批判的な内容になると思う。
批判なら書かない方が自分の立場的にもいいのだけど、でも書かなきゃいけないなにかがこの映画にはあるような気がしている。どういう構成にするか迷ったが、前半である程度否定的な意見を書き、後半に良かったと思う点を記す。
あと、ネタバレを多分に含んでいるので、このテキストを読む人が果たしているのかどうかは甚だ疑問だが、とりあえずそのことも断っておく。
まず映画がはじまった瞬間に、わたしは「嫌な予感」を抱いた。
この映画は「未完成映画予告編大賞」の第3回グランプリを獲得したことで製作されたものらしい。そして同賞の「堤幸彦賞」を受賞したのだという。それらが上映前にクレジットされたのだけど、その瞬間、具体的には「堤幸彦」という文字を見た瞬間にギクッとしてしまったのです。
正直に言うとわたしは堤作品が苦手で、もしやこの作品もそのテイストが、、、などと思ってしまったのです。そしてその嫌な予感がある程度的中した。効果音の付け方、唐突な前衛っぽさ、強引な「泣かせ」、なんか堤幸彦イズムを随所に感じてしまった。こればっかりはどうしようもないというか、ごめん、俺はちょっと、、、っていう感じ。すみません。
以下、劇中で解せなかった点を列挙します(記憶を頼りに)。
・ライブハウスの外でのシーン。アシバーの男とマーミー、ハルが対峙するところ。
アシバーの男は無秩序に銃を発砲し、おそらく客引きをしていただろう娼婦の女性が一人殺されてしまう。
だがそこにいるたくさんの人たちは、驚くどころか女性を気にすることも逃げ出すこともしない。ただ立ち尽くしてぼんやり様子を見ている。
それほど「諦め」があの当時には蔓延していた、ということの表現なのだろうか? だとしても、あの女性の顛末は不憫でならない。ただ殺された人。
後から駆けつけたバンドメンバーも、その女性に一切注意を払わない。誰一人として彼女のことを気にしない。
物語上関係のない人物だからといってああいう処理の仕方をすることはどうなんだろうか。
・マーミーって結局逮捕されたの? 犯行後ハルと逃げた後、なんか意味深っぽいダンスシーン(あれダンス? なんの舞?)をした後で、警察に逮捕されるシーンは描かれなかった。
ていうか、普通にいたよね、たとえばビリーの戦死がナレーションで伝えられるシーン。あの屋上で。マーミーいたよね?
いつ逮捕されたの? そこはっきりしないから、後半でのマーミーの息子(翔太の父親)が手紙を見て真実を知るシーンもなんかボヤけてしまう。
わかるんだけどさ、ああ、逮捕されたんだなって。でもそこ描かないとあそこ弱くなんない?
・ビリーが日本語ペラペラだった件、あれ何? なんで最初は英語でしか話さなかったの? 理由がわかんない。あそこで唐突に日本語で話したのもわかんない。何を狙っていたのか。
たぶん「自分はアメリカ人でも日本人でも沖縄人でもない」っていうことを語らせたかったからだと思うんだけど、それだったら最初から日本語も英語も流暢に使いこなす陽気なビリーって感じで描いてた方が、それでもそのどれにもなれなかったビリー、、、って感じで効果はあったんじゃなかろうか。
・マー坊の妹が実は米兵に殺されていたという設定。
マー坊がアメリカーを嫌っているっていうのは描かれてたけど、たとえばときどき首元のリボンを無意識に触ってるとか、そういうの描いとけばあの告白もポッと出には感じなかったんじゃなかろうかな。
なんかアシバーのシーンで女性を意味もなく殺してるシーンを通過してるからか、ここでも女性の死を物語の盛り上げに利用しているようにも感じられたんだよね。まあ、それくらい理不尽で怒りのおさまらない事件が実際に起きていたことは事実なんだけど。
・コザ暴動が起きる直前、夕暮れ前の川辺かどこかで、ハル(になった翔太)が一人たそがれている。そこに、ウィッグとサングラスを外した辺土名さんがやってきて、励ましとも言えない無駄話をしている。そこに、平良さんがオープンカーでやってきて「街が大変なってるぜ」と告げる。
ここ!
これってこの後の「コザ暴動」に入っていくシーンなんだけど、まず、コザ暴動って深夜に起きたことだよね。なんで日が沈む前に発生していることになっているの?
それに平良さんはなんであんなに悠長なの? あの余裕の構えで迎えに来たんだったら、その後のシーンで、つまり暴動の最中で焦燥感に駆られた演技との釣り合いが取れないよね。あの騒動の中で感情が混乱しているっていう解釈は可能だけど。
と、苦言をくどくどと並べ立てているけど、良かったところも大いにあった。
まずは役者さんの演技。言葉づかいも自然だし、県内の役者さんたちが生き生きと躍動しているなというのは感じた。
たぶん監督さんは、役者さんを生き生き演技させる力量が秀でているんだろう。個性を活かしているというか。たとえばカフェやバーで駄弁ってるときの自然な空気感、安心感。
なんとなくだけど、ストーリーとしての起伏があまりないようなもののほうが向いているんじゃないだろうか。あの楽しげな感じって、たとえばクドカンのドラマだとああいう拠点みたいなところでの掛け合いが面白いんだけど、ああいうのを感じた。
いままでの沖縄を描いた作品と比べてみても、会話の自然さや面白さはトップクラスなんじゃないか。監督のつくるシットコム的なものを是非見てみたいなと思った。
印象に残った役者さんは多いが、桐谷健太さんはまずもう、「俺たちの桐谷健太だ!」って感じでサイコーだったし、やっぱり役者として華があるなって思った。
その桐谷健太と入れ替わる翔太役の津波⻯⽃さんは、ペナルティーのワッキーみたいな奇怪なダンスも上手かったけど、演技も良かった。関係ないけどマーミーのダンスがあのワッキーダンス(「ごきげんダンス」だっけ?)だったら俺は死ぬほど爆笑してこの映画大好きになってたと思う。雰囲気ぶち壊しだけどこれこそロックだ!
閑話休題。
あと過去シーンでのインパクトのバンドメンバーはみんな良かったな。あそこを演技力がありかつ若くてエネルギッシュな県出身の俳優で固めたっていうのが、過去シーンを瑞々しく見せていた大きな理由だろうなと思う。
脇を達者な俳優やユニークな芸人さんらで固めたのも良かった。ベンビーさん、すごいうまいなぁ。シリアスな演技とかももっと見てみたいと思った。
コザ暴動のシーンに登場したOZEの新垣さん。あの迫力はやばかった。登場シーン少ないけど、存在感は凄まじかった。
それから喜舎場泉さん。じいちゃんが乗り移った翔太に呼び捨てにされ「ターがシージャーか?」と捲し立てるところはめっちゃ笑った。
あと、ちょっと名前わかんないんだけど、過去シーンで平良さんにピックを選んでもらえなかった方の女性。ハルに「お前なんかハブに噛まれてしまえ」というところ、あそこは笑った。なんだろう、言い方とか間とか表情とか、めっちゃ好き。
よかったといえば、やはり音楽。音楽は素晴らしかった。もっとガンガン使ってもよかったと思うくらい。
ミュージックタウンで歌った最後のORANGE RANGEの曲以外は全部良かった。最後のだけ、「あれ? 俺たちのロックンロールは?」みたいな感じになっちゃったから、あの曲じゃなくて良かったんじゃないか。
そもそも物語の設定だとインパクトのメンバーが作曲したことになってるから、「それであの曲?」ってなっちゃうんじゃないか。そこがもったいなかったな。
でも全般的に音楽は素晴らしかった。ラストの紫が登場するところ、フルで聴きたいって思うほどカッコよかった。あんなにカッコよかったんだって、知らなかった。すんません、舐めてました。