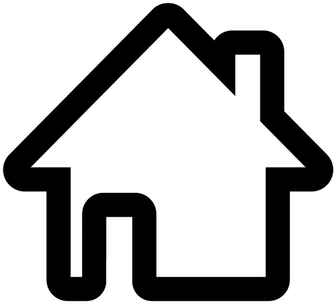宜野湾市のカフェ・ユニゾンにて、先日とあるイベントに参加して来ました。っていうとなんか出演したっぽい書き方ですが、そうじゃなくて、ただ単に飯食って酒飲んでトークやライブを聴いたってだけなんですが。
そのイベントは、『鶴と亀』という、じいちゃんばあちゃんの可愛らしくユーモラスな肖像写真を収めたフリーペーパーを製作しているカメラマン・編集者の小林直博さんと、沖縄県内で活動するラップユニットMCウクダダとMC i know さんのトーク&音楽ライブ。
小林さんが撮影した写真をプロジェクターで投影しながら、その写真にまつわる話をして、それにウクダダi knowが質問したり茶々を入れたり、そうやってトークが展開されていく。その写真と裏側のエピソードがすごく面白くて、なんて楽しい時間だったのでしょう。
『鶴と亀』の写真に入り込んでいるのは、被写体の老人だけではない。彼・彼女の生活のなかにある、細やかなディティール、取るに足らないストーリー。それらをまるごと写し取ったのがあの写真なのだ。それは、鑑賞者が見ているだけではわからない、教えてもらわなきゃわからない。だから撮影者がトリヴィアルなエピーソードを語ってくれる機会はとても貴重だ。

『鶴と亀』自体は、長野県の奥信濃で撮影・製作されているのらしいけど、全国いろんなところに置いてあるらしい。小林さん、せっかくなのでと沖縄のじいちゃんばあちゃんたちを撮影してそれもスライドで流してたのだけど、それもまた可笑しかった。長野のご老人とはまたちょっと違うのだって。ただ、総じて沖縄のじいちゃんばあちゃん(に限らず多くの人)はシャイなのだとか。
そのトークのなかで、印象に残った話があった。それはウクダダi know両者の祖父母について話していた時のこと。
ウクダダさんの祖父母は父方母方ともに健在らしく、父方の祖父母は95歳くらい、母方の方は85歳くらい、とのことだった。そして彼女は「当たり前だけど」と前置きをしつつ、でもそれでいて強い語調で言った。「80代のじいちゃんばあちゃんと90代のじいちゃんばあちゃんは、全然違う!」。そこで会場に笑いが起きたのだけど、ウクダダさんは構わず続ける。「10代と20代じゃ全然違うみたいに、80代と90代じゃ全然違う!」
「おじいちゃん・おばあちゃん」と括ることで、ひとつの枠の中にギューっと押し込めてしまう、そんなふうに見方を規定してしまう力が「おじいちゃん・おばあちゃん」という言葉にはある。というか言葉のそもそもの本質が視点の規定なのだけど。
「時間」は若者だけの専有物ではない。この当たり前のことを、わたしたちはときどき忘れそうになる。「老人」という言葉で括って、そのカテゴリーに入った人たちにはあたかも時間が存在していないような感覚に無意識のうちになっちゃってないか、ってわたしはものすごく心がざわついた。
ウクダダさんの言葉を聴いたとき、わたしは思い出したことがあった。ドキュメント72時間という番組で、バラック飲み屋街「塙山キャバレー」を取り上げていた回。75歳くらいのスナックのママが、別の店舗の85歳くらいのママに相談をしているシーン。若い方のママが「わたし、この仕事向いてないと思うんです。人と話すのが苦手で」と悩みを吐露し、先輩ママは「もうちょっとだけ、頑張ってみようよ」と返していた。このシーンにわたしはなぜかとても感銘を受けていたのでした。
そのフラッシュバックがザワつくわたしのこころにさらに覆いかぶさって来たのでした。
当たり前のことですが、ひとはいくつになっても、生きているのです。
それを日常の中で感じている彼女たちの視線や感性に、わたしは感服したのでした。
その視線って、彼女たちがラッパーだから持ち得たものなのだろうか。ふと、そんなことを思った。でも正直わかんないけど。人それぞれだろうし。
ただ、彼女たちはどうしてラッパーになろうと思ったのかな、というふうなことも思った。
ラッパーという存在って、生活の「リアル」を演じる「アクター」の要素もある。そのリアルをリリックとして立ち上げる「作家」でもある。要するに「自作自演家」である。
彼女たちにとっての「リアル」は、ヒップホップの初期形態としてあるような、窮屈で貧しく阻害され不可視化された者たちの「カウンター」や「ポリティクス」なものとは遠くにあって、ある程度成熟した社会で取り立てて不自由を感じていない生活者としての視点から作られ、演じられている。
さて、そうなると、彼女たちにとっての表現欲求はどこから発生してくるのだろうか。切実な、魂の叫び的な、これを言わなきゃ伝えなきゃ、というような事柄って果たして生まれてくるものなのだろうか(事実、後ほど述べるままごとという劇団の作品『ツアー』の終演後のアフタートークの中で、「崇高なメッセージみたいなものは特にない(*個人的要約&解釈)」(i know)と述べていた)。
ここから先は、わたしの想像。たぶん彼女たちにとって、音楽やラップというものはそれほどスペシャルなものではない。リアルを表現するものではなく、生活の中に溶け込んでいるものである。つまりリアルそのものである。美味しいご飯を食べたり友人とおしゃべりをしたりバラエティ番組を見て笑ったりするようなものと並行して音楽(ラップ)がある。だから、彼女たちにとってのラップという表現形式って、リアルなものではあっても自身のコア(アイデンティティ)とはそれほど結びついてはいないんじゃないか。重ねて言うと、別にラップじゃなくたっていいんじゃないか。
だからこそ、パッションやエモーションなどが湧出するような詩的あるいは感情的な部分へのこだわりはそれほどなくて、もっと物理的な部分での「遊び」を重視している。んじゃないかと感じる。これは、ハンドルとかの「遊び」でもあるから「ユルさ」とも言えるかも。その「遊び」=「ユルさ」のほうこそが彼女たちをアイデンティファイしている。だってさ、ライブ中に「今日ナンパされた〜」「え、どこで? ちょっと待ってどうゆうことそれ聞いてないんだけど」「なんで怒ってんの?」「いや怒ってるとかじゃなくて詳しく聞きたい、えまじ、どこで?」「国際通り」「は〜まじ? え、誰に?」「え、外国人」「外国人か〜」とかって話をはじめましたからね。後ろでDJが曲流してるのにこのおしゃべり全然おわらなくて「いまライブ中だよね?」とかって痺れを切らして注意しちゃってましたからねDJさん。曲の途中でビール注文しに行っちゃうし、寝っ転がってビールを飲み始めちゃうし。むしろ「遊び」しかない。いいな〜。

(いちおうコレ、ライブ中ですよ)
さて、このMCウクダダとMC i know を知ったのは、ままごとという劇団の公演だった。『ツアー』という作品の沖縄公演最終日でのアフタートークに、ふたりが出演していたのだった。
ままごとといえば、岸田國士戯曲賞を受賞した『わが星』などは、ほぼ全編がラップでできている。地球が生まれてから消滅するまでを、一人の少女が生まれて死ぬまでと重ね合わせて描いた作品だが、台詞や音の使い方などを取っても、ラップあるいはヒップホップへのリスペクトが見える。だからなのでしょーか、アフタートークがこの人選になったのは。
全編ラップの台詞で演劇をつくるなんて、これ「遊び」以外のなにものでもないでしょ、とわたしは思ってる。それは演劇の文脈から見ても、ラップの文脈から見ても。だって(わかんないけど、でも絶対に)「構造」が先にあるから。「台詞がラップになってる劇作ったら面白いんじゃね?」ってところから発想してこの作品はできてるはず。ままごとという劇団(あるいは柴幸男という劇作家)はおそらく、構造というかアーキテクチャというか、そういうものに萌えているはず。だからたぶん、柴さんはきっと工場とか好きだと思う。ジャンクションとかもきっと好きなはずだ。なぜなら、わたしがそういう「構造」が好きであってかつその部分の琴線に触れてままごとが好きになったから。そのはずだ。そうであってくれ。
さて、この『ツアー』という作品も、やはり「構造」が先にある。アフタートークで柴さんが語ったように、まずは時間から決めた。30分。っていうのも、ままごとではおなじみの口ロロの楽曲(「ツアー」)が30分で、この曲をまるまる使って演劇を作るから。流しっぱなしで曲の初めから終わりに合わせるように物語もはじまっておわる。その予定で作り始めた。らしい。だが、実際に上演時間に合わせてプロットあるいはストーリーを組み立てていく(必然的に時間が「飛ぶ」ことになる)プロセスの中で、曲の「流しっぱなし」ではなくなり、時間も45分に伸びた。でもそれをはじめにあった構造(30分&曲のフル使用)にギチギチに当てはめずに、伸びたもんは仕方ないよねーそだねーってルーズな感じで作ったことが逆に善き、なんて思うのですわたし。
ただ、もし昔のままごとだったら(って全然知り合いでもなんでもないから想像ですよ)、もうちょっとギチギチにしてたんじゃないかと思います。そう感じられたのは、『ツアー』上演の2日前に開催された、ままごと過去作品の上映会に行ったから。そこで上映されたのは2015年版の『わが星』(『朝がある』という作品もやってたけど間に合わなかった)。僕が観たことがあったのは2009年版の『わが星』。同じ作品なのだけど、2015年版のほうが「余白」が多かったように感じられたのです。先ほども書いたように『わが星』はラップの演劇です。もうちょっと詳しくいうとラップミュージカルです。口ロロの「00:00:00」という楽曲と時報に合わせて台詞が話されるのですが、その台詞は音に合わせて嵌められていきます。その台詞が2009年版はガチガチに詰め込まれていたのですが、2015年版はちょっとルーズ。間を開けたりハイフンを入れたり(つまり言葉を伸ばしたり)、そんなふうに微妙にでも確実に変えられていた。ままごと=柴幸男は、よりルーズな、より「ユルさ」の方向へと生成変化をしていたのでした。
実際アフタートークの中で柴さんは、「演劇界に革命を起こす!みたいな熱意もかつてはあったように思うが、もうないですね」と身も蓋もないことを言っていた。「だからカフェみたいなことやってます」とか。
そしてこの『ツアー』に関しては、構造の組み立てとゆるやかな瓦解が作品のなかで同時に起こっている。作りながら壊す、壊しながら作る。構造の中で生まれた主人公の行動、感情、営み、それらが見せるあらゆる運動を、余裕を持って見つめる眼差し。『ツアー』という作品全体から、そんなようなものが想像されたのでした。移ろったり膨らんだりする登場人物たちの何か(感情なのか感覚なのか意識なのか関係なのか)に合わせて構造の方を設え直す。だからはじめにあった設計図と比べると、はみ出したり歪んだり、そのようなことが起こる。でも、このほうが暮らしやすいよねそだねー、ってのが今のままごとなのだ(ってだから想像だよ。昔からそうかもしれないし。でも知らないからこそ言えることもあるよねそだねー)。
さて、長いこと書いてしまいましたが、そろそろ終わります。
えっとつまりいいたいことは、誤解を与えるような言葉になるかもですが(どうせ読む人少ないからいいかな?)、ままごとは「老い」ている、ってことです。これは、否定的な意味ではないんです。「隙」ができてる。『鶴と亀』に登場するようなじいちゃんばあちゃんに近づきつつある、ということです。
歳を重ねると頑固になる、という一面もあることはあるのかもしれません(そういう言葉によってわたしたちがそういう見方に縛られている可能性もないことはない)。ただ、『鶴と亀』に登場する御老人たちの魅力は、隙、ツッコミどころ、ユルさ、それらが満載なところ。そこがすこぶるチャーミングなわけです。ままごとも、そのような「老い」方をしているんじゃないかなと思っとるのです。無論、30代中盤くらいだと思うのでまだまだお若いのだけど、劇団としてそのようにチャーミングな老い方をしていくのだと想像しているのです(勝手に)。