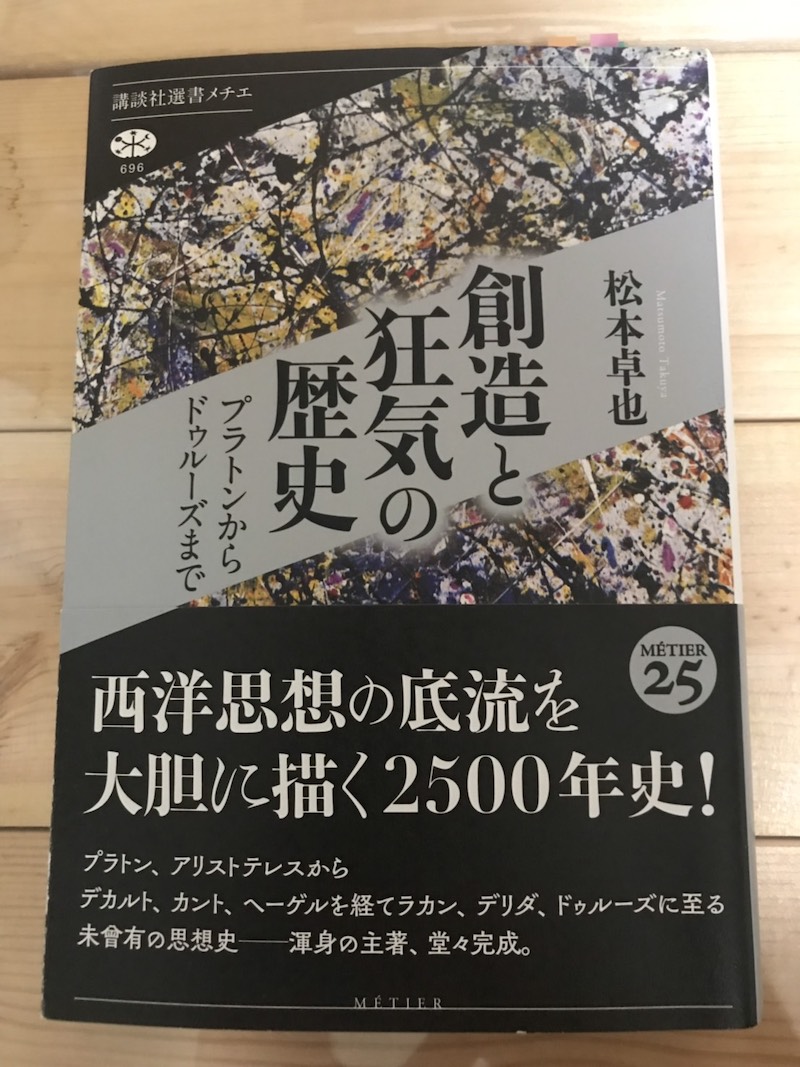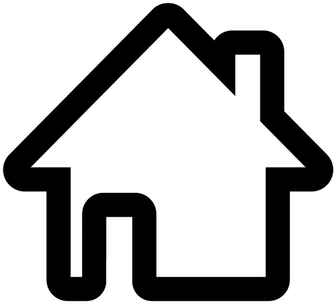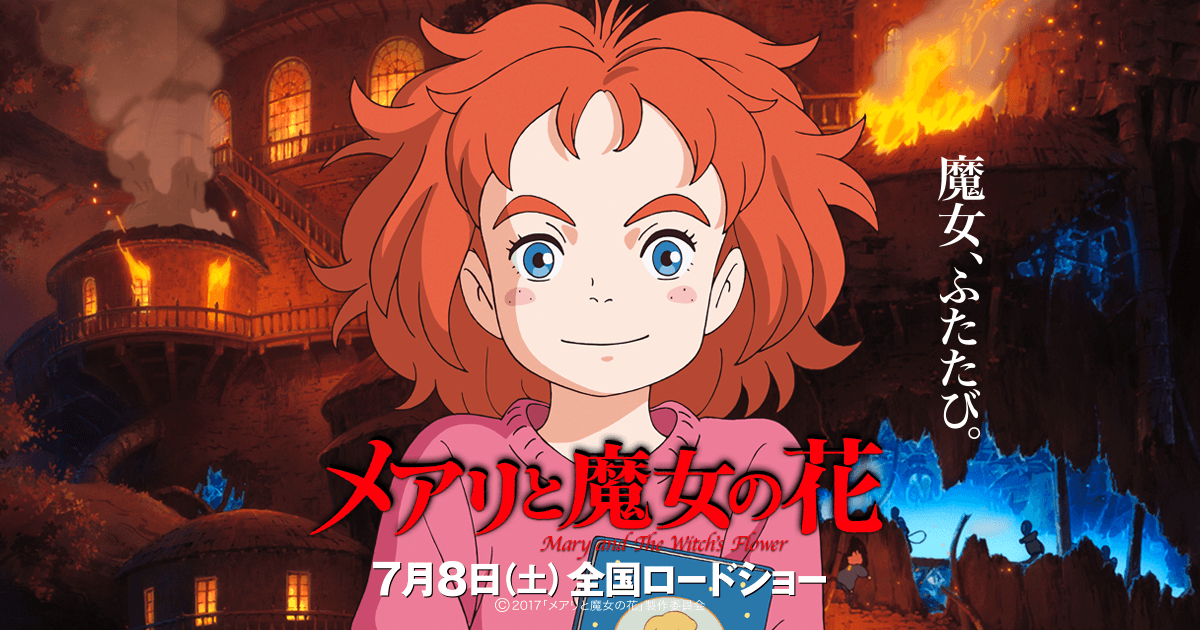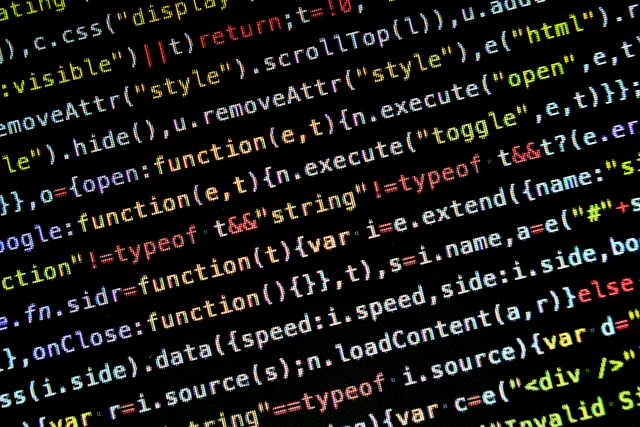わたくし兼島が、保育園の保護者向けに行った「言語」についての講話の内容(文字起こし)です。
当初は他のことを喋ろうと思ってある程度準備していたんですが、途中からタガが外れたかのように思いついたことをバーっと喋っちゃいました、、、笑
でも、大事なことなのでいいよね(ニコッ)
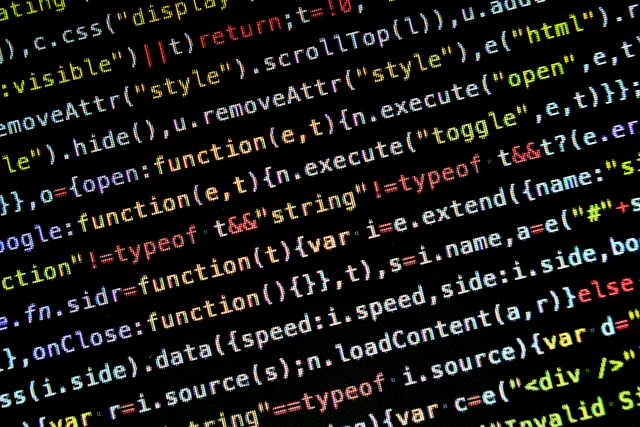
『言語についての講話(第1回)』
(2017年5月、@エンジェルズスクール)
こんばんは。今日は、忙しい中ご出席いただき、どうもありがとうございます。
えーっと、今日はですね、今日はというか年間を通してこの勉強会においては、H先生と僕とで半分半分ずつ時間を使って、H先生の方が、主に「おしごと」の、あるいは普段の保育や日常の中でモンテッソーリ的な見方をどのようにしていったらいいか、どのように子どもたちを観察していけばいいか、そういった観点からH先生に話してもらいます。
で、僕はですね、主に「言語」のことをやろうかと。
一応「言語」っていうのは、モンテッソーリ教育の中でも大事なことで、おしごとの中にもちゃんと言語の教具や教材があったりします。なので、一応H先生がやることの守備範囲に、その枠組みの中に言語は含まれてはいるんですね。
でも、なんで今回、今回だけじゃなくて今年度の勉強会では、僕が担当する部分は全部言語についてやろうと思うんですけど、なんで言語をわざわざやろうかってことなんですが、簡単にいうとですね、モンテッソーリ教育の枠組みの中では収まりきらないからなんですね。言語が。
ちょっと勉強すると、まったくもって意味がわからないというか、いろいろとややこしいことだらけなんですね、言語って。
あまりにもわからないことが多すぎる。
例えば、それこそ「言葉をどうやって獲得するか」とかって、ビシッと説明できるようなメカニズムが解明されてないんですね。はじまりからして全然わかんないっていう。
でももっと不思議なのは、ぜんぜんわかってないのに、フツーに使いこなしてるってことですね。
どこで手に入れたかわからないものを上手につかいこなす能力っていうのが、そこが人間のすごいとこだと思うんですけど、でも謎ですよね。
たぶん普通に生活してたら、あんまり言語のその不思議さみたいなのって、あんまり意識しないと思うんですけど、一回意識するともう全然わかんないんですよね。僕はもう毎日意味がわからないんですよ、だから。
なので、今日は、お母さんたちにも意味わからなくなってもらおうと思ってます。
ほんとはですね、今日は最初なので、言語っていうのがモンテッソーリ教育の中でどう捉えられてて、教育のなかにどう位置付けられてるのか、みたいなことを話そうと思ってて、一応それで資料というか、ほぼ論文みたいなものも途中までですけど書いてたんですよ、概要みたいな。
でも、一回みなさんに意味わからんくなってもらって、そのあとで一個ずつ中身に入るっていうか、言語のことを一個ずつ考えていくっていう感じにしたいんですね、1年通して。
で、今年度の勉強会が終わったときに、言語についてちょっとでも新しい考え方とか、発見とか、役に立ったとか、そういった感じになってればいいなと思います。それを一応この勉強会での、僕の担当する「言語」のパートでの目標にしたいなと思います。
なので、今日は最初なので、意味わからんやつをやります。
***
まず、言語についてっていっても、言語とはなにか?みたいな話をやらないといけないんじゃないかなと思ってます。
「言語」っていうより「言葉」って言った方がいいですかね? 言葉って、たぶんいろいろとあると思うんですけど、コミュニケーションの手段っていうふうな捉え方がいちばんメジャーなのかなって思うんですね。伝える道具っていう。思ったこととか考えてることとかを、お互いに表現し合う、伝え合う、っていう、そういうものだと考えられると思うんですね。
でも、じゃあここでちょっと考えてみてほしいんですけど、お互いの感情とか考えを伝える手段ってことは、まず自分の考えてることがちゃんと言葉にできて、それが相手に伝わって、言ってることをわかってもらう、っていう流れで言葉は使われるわけですよね。
つまり、言いたいことの方が本質で、言葉っていうのはその表現手段ってことになりますよね。
言葉が伝達の道具だとすると、たとえば普通話す時って、わざわざ回りくどい言い方とかやるじゃないですか。婉曲表現とかっていうんですけど。
もし伝達手段なら、ストレートに言った方がいいんじゃないかって思いません?
たとえば「今度ご飯でも行きましょう?」って言われて、「いまちょっと忙しくて、、、」とかって断るのとか、よくありがちな返答だと思うんですよ。
でもこれ考えたら、「行けません」っていう答えの方が、道具の使い方としては正しいですよね。よりストレートに過不足なく伝えてるじゃないですか。
でも、ほとんどの場合こんな使い方しなくて、「忙しくて、、、」とか「いまちょっと金欠で、、、」とか極端なのだと「あぁ、、、」みたいな。わざわざそういう曖昧な使い方をみんなするんですよね。察して!みたいな。
道具としてはちょっと不便じゃないかなっても思うんですよね、そうなってくると。
洗濯機があるのに川に洗濯に行くみたいな感じじゃないですか。一応こういう比喩表現とかも道具としてみると無駄ですよね。
あと、「負けは負けだ!」みたいな言い方あるじゃないですか。
これって、よく考えたら当たり前のことしか言ってないんですよね。情報としては〈1=1〉ってただ同じこと繰り返してるだけなんですよ。
でもこの表現って、有無を言わさぬっていうか、強い圧力ありますよね。
「負けは負け」とか「私は私」とか「ヨソはヨソ、ウチはウチ」とか、道具としては何もしてないんですよ。
いま言ったようなこととかって、結局、相手を信用してないとできない表現なんですよね。
相手がこの意味をわかってくれるだろう、って思ってないとできない言い方なんですよ。
曖昧な言い方で伝えるって、道具としては中途半端な使い方だし。
直接相手の家まで行けばいいのに近くのコンビニで待っとく、みたいなことを、普段言葉を使うときにやってるんですよね。
とかってやってたらいつまでも終わらないので、ここらへんで一応ストップします。
要は、言語というのは、道具は道具でも、あまり直接的で合理的な道具ではないってことですね。だいぶ無駄を孕んだものなんです。その部分は、まあ当然みなさん思うことだと思います。
言葉は無駄を孕んだ道具って考えるとして、じゃあなんでいちいち無駄が入り込むのか?っていうのが今度は問題になってきますよね? きません? きますよね!
なんでわざわざ無駄なことをするのかって考えたら、無駄なことをすることで何らかの効果が得られるからだと思うんですね。
さっき婉曲表現って、デート断るのも直接言わずに「ちょっと忙しくて、、、」みたいな曖昧な言い方をするって話がありましたけど、あれもし直接断ると棘がありますよね。グサッときますよね。
そのグサって相手を刺さないために、やんわりと相手の傷を最小限にとどめる気遣いみたいなのが、「ちょっと忙しくて、、、」っていうフレーズには含まれてるんですね。
つまり言葉だけ、言葉だけっていうか音としてただ聞くと、「忙しい」ってただ言ってるだけの表現なんですけど、でもそこの裏側に「ごめんなさい、あなたとはデートに行けません」っていう丁重なお断りの意味が含まれてるわけです。
文脈とか状況とか関係性とかで、そういうふうな含みを言葉に付け加えて届けてるんですね。
こういう文脈とかから言葉を見ていくのを「語用論」っていうんですけど、そういうふうにして人は言葉を使ってるんですね。こういうのができるように道具としての無駄がたぶんいっぱいあると思うんですよ。
「忙しい」って単語を辞書で調べても、「ごめんなさい、あなたとはデートに行けません」って説明は絶対に書かれてないんですけど、でもそういう意味なんですよね、ここでは。って考えると、ここでもまた新たな問題が出てくるんですよ。
ふつうに考えたら、辞書を引いた時にそこに書いてある説明が、その単語の意味ってことになるじゃないですか。
でも、人が話している時に使っている言葉は、その辞書に書いてある意味からズレちゃったりすることがよくある。
そしたら、「意味」って何? ってことになっちゃうんですよ。
辞書を読んでたら、単語には固定された、その単語本来の意味があるっていうふうに思っちゃうんですけど、でもあれは、固定された正しい意味じゃなくて、あくまでも代表的な意味だと考えるべきなんですね。
「だいたい皆この言葉はこういう意味で使ってるよね」っていうなんとなくの了解がその単語の意味ってことで辞書に書かれてる。だから、ある語句とその意味とがきっちりセットってわけじゃ必ずしもないんです。
本来、辞書って、あるいは文法書とかもそうなんですけど、そういうのって、その言語を使う人が普段喋っている言葉を集成して編まれていると思うんですね。つまり、発話の集積が規則を作り出すんです。
ウィトゲンシュタインっていう哲学者がいるんですけど、この人が、「語の意味とはその使用である」って言ってるんですね。さっきいった語用論っていうのもこの人の影響をだいぶ受けてると思うんですけど。
ともかく、その言葉に意味があるんじゃなくて、どう使われてるかっていうのを追っていく必要があると。それが意味だと。
辞書とか文法書は、言葉がどう使われてきたかっていうのが表現されてる書物なんですね。
ウィトゲンシュタインについてはまた後ほど触れることになるかと思います。
そうやって、言葉の決まり、規則が出来上がっていくんですけど、でも一旦規則ができると、今度はその規則が発話を規定するようになってくるんですね。
「正しい日本語」とか「言葉遣いが乱れている」っていうのは、そういう認識のもとにしか生まれないと思います。
実際の発話行為を、規則を参照して成否の判定をする。
そういうプロセスを経るから「正しい」とか「乱れている」とかが言えるんですね。
そしてこの言語の規則が権威化してしまって、辞書とか、文法書とか、そういうのに書かれているのが正しい言葉だと考えるようになります。
この言語の規則に発話行為が規定されるっていうのが、また次の重要な問題になります。
さっきから問題が出てきすぎな感じがありますが。
規則とか言語体系とかっていうのは、人に、言葉の使い方を規定するようになります。
ただ使い方だけじゃなくて、物の見方とか、考え方とか、そういったことも、言語は規定してくるようになるんです。
たとえばオオカミと犬の違いってなんなのかって考えるとき、まあいろいろ生物学的な違いがあると思うんですけど、言語学的に見ると、「名前(呼び方が)違う」、っていうのが一番の大きな違いってことになるんですね。
どういうことかっていうと、名前によって、両者の間に線を引いたって考えるわけです。
姿形からしたらオオカミのことを犬って呼んだっていいはずなんですけど、本当は。でも大昔の人たちは、犬とオオカミの間に何らかの違いを見出して、片っぽを犬、片っぽをオオカミって呼んだ。その分類がいまもずっと使われている。そういうふうに考えるんですね。
だから名前をつけた、言葉を与えたことによって、オオカミっていう存在が誕生した。まあ実際にはもう絶滅しちゃいましたけど。
犬も同じで、もともと犬として存在していたわけじゃなくて。ほかのいろんな動物たちとの間で違う部分を見出されて、だからわざわざ他と別の名前で呼ばれるようになった。そのあとで「犬」として存在するようになった。
なので、名前や概念を与えられてはじめて、存在することができるわけです。つまり人は、言葉によって世界を切り分けて、分節化して見ているんですね。
もともと全体としての世界があって、それを切り分けて一つひとつの言葉と概念(物)が同時に誕生した。
だからその言語体系全体のなかにその言葉がどう位置付けられているか。あるいは他の言葉とどのような関係にあるのか。
言葉の意味っていうのは、その関係性があってはじめて成り立つものなんですね。
その関係性のあらゆるパターンというか、世界の切り分け方というか、そのような物の見方が、言語の規則としてまとめられていくんですね。
そうすると今度は、その規則を参照する人は、次第にそこに規定された物の見方をするようになる。オオカミと犬は別のものだという考え方がデフォルトになる。
というふうにして、言語の規則が、物の見方や考え方を規定するようになるってことが言えるんですね。
こういうような言語観を「言語相対論」っていうふうにいいます。
「言語が思考に影響を与える」っていう考え方ですね。これをもっと極端にして、「言語が思考を決める」って考えるのが「言語決定論」って言います。
でもさすがに「決定論」までいくと言い過ぎだろっても思うんですよね。なのでバランス良く「言語相対論」でもって僕は言語を捉えるようにしてるんですけど。
もうひとつ例を出すと、さんぴん茶ってあるじゃないですか。あれって、ジャスミン茶のことですよね。でも沖縄の人はさんぴん茶っても呼ぶ。両方使えるんですね、沖縄の人は、さんぴん茶もジャスミン茶も。
でも、たぶん沖縄の人ならなんとなくわかると思うんですけど、なんか違いますよね。
なんか、さんぴん茶の方は土着感ありますよね。ジャスミン茶の方が小洒落た感じありますよね。オシャレなカフェならジャスミン茶で、沖縄っぽさ全開の古民家カフェならさんぴん茶ですよね。
このなんとなくの秩序は、「ジャスミン茶」だけしか使わない人にはわからないんですよ。
こういうふうに日常的な言語に物の見方は規定されてるんですね。大げさにいうと、イデオロギーがあらかじめ組み込まれてしまうってことです。
そのようなものの見方をするように仕向けられているってことですね。
***
ここまでが、言語、言葉について、言葉とは何か、ってことを考えてきたんですけど、ここからが本論です。前置きが長い!っていう、、、すみません。
ここから、発達と言語のことを考えていきたいと思うんですけど。まずですね、発達心理学の有名な学者さんに、ピアジェって人がいるんですね。この人の話からはじめたいと思うんですけど。
このピアジェさんはですね、いまもたぶん心理学科では普通にこの人の理論習いますし、教育学部とか保育士の養成課程とか、僕自身も社会福祉士を取得する際にこの人の発達段階説っていうのを勉強しました。
さらにいえば、ピアジェの理論モデルって、モンテッソーリの理論と類似しているんですね。
どちらも子どもを観察することによってそれぞれの発達段階理論、発達モデルを形成していったので、共通することも多いです。今日はモンテッソーリ勉強会なので、ピアジェの理論を参照しながらモンテッソーリについて話すってことかと思いきや、ここではモンテッソーリはスルーします。さっき言ったように、言語についてはモンテッソーリ教育の枠組みでは捉えきれないことが多いので。
なので、ピアジェの理論もここで詳しくは述べませんが、ごく簡単に言うとピアジェの理論というのは、未熟で自己中心的な幼児が、だんだんと他者の視点・マクロな視点を獲得していき、それに伴走するように具体的思考から抽象的思考へと進んでいく、っていうような考え方です。
で、このピアジェさん、論敵がいてですね、二人いるんですけど、一人目がワロンっていう人です。
このワロンさんは、ピアジェの子どもの発達モデルは「個人主義的」なんじゃないか、ってことを言ったんですね。
ピアジェの考え方では、いちばんはじめからあらかじめ「私」が確立されていて、最初はひとりの狭い空間の中だけで活動したり考えたりすると。そして次第に周りの人たちや離れたところにも意識が向いていく。
ワロンはその理論の出発点に疑問を投げかけてます。「はじめから「私」と「他者」が分離してるけど、それ本当?」ってことですね。
ワロンは、まず全体があって、「私」と「他者」の区別っていうのはあらかじめ存在しない、っていうことを言いました。
はじめは、私=世界なんですけど、それがいつからか世界が分節されて、「私」とそれ以外=「他者」っていうふうになると。
その分節化がどんどんどんどん進んでいくのが発達なんじゃないか。ごく簡単にですがまとめると、こんなことを言ってます。
このワロンの理論って、さっき出てきた、言葉が世界を切り分けている、っていう捉え方とリンクしてるっていうのがわかるかと思います。
ただ、この論争のどちらが正しいとか、そういうのはよくわかりません。当時はワロンの方が優勢だったということですが、でもワロンは授業で習いませんでした。このへんのところは僕もよくわかんないです。
で、さっきピアジェに論敵が二人いたって話だったんですが、もう一人がヴィゴツキーという人です。この二人が争ったのは「内言・外言」という概念についてです。
内言っていうのは、「音声を伴わない言葉」のことですね。頭の中で考えたり整理したりするときも、言葉って使いますよね。そういう頭の中だけで使うのを「内言」っていいます。
で、「外言」は逆で、音声を伴う言葉のことですね。伝達の道具として捉えられるものです。この「内言」と「外言」では、どっちが先に発達するかっていうのが、二人の論点だったんですね。
ピアジェは、彼の理論を考えると予想できると思いますが、内言→外言っていう順番なんですね。
自分の中で考えるようになって、それが徐々に周囲に向けて発せられるようになる。これがピアジェが言ったことですね。
逆にヴィゴツキーは、いやいや、言語っていうのは他者によってもたらされるんだから外言→内言でしょ、というふうに言った。
言葉がどう使われているのかを把握した後でしか、頭の中での言葉は使えないということですね。この論争も、ヴィゴツキーの方に軍配が上がりました。ピアジェ2連敗です。
ワロンとヴィゴツキーはどちらも、全体との関係性あるいは他者との関係性を各々の発達理論に持ち込みました。
ワロンは発達を私=世界が切り分けられると見立て、ヴィゴツキーは他者の言葉やその働きかけが私の思考を形作るとしました。
この「切り分け」や「他者」というキーワードから派生して、もう一人取り上げたいのが、ラカンという人です。
ラカンは、精神分析の人です。フロイトってご存知ですかね? フロイトは精神分析のパイオニアなんですが、その人の正統的な後継者だとラカンは自分で称しています。
ここで精神分析について説明すると大変なので今日はやりませんが、いろんな文学や映画などの解釈などにも使われたりしています。で、ラカンなんですが、この人の言ってることがまぁ難しいんですね。やたらと変な概念をいじり回して語るので、絶望的なくらい意味がわからないってことがよくあります。
ラカンは、「私」という存在の認識と、言葉とが、とても大きな関係を持っているってことを言いました。
もともと乳児っていうのは、母親と同一化しているっていうふうに考えたんですね。母親とずっとくっついて、食事のときも排泄のときも。
そのときの赤ちゃんというのは、とても安心感に満たされていて、私=母親なんですが、さらに母親=世界でもあるんですね。母親だけで世界が成立している。それでいて私は母親と同一化している。つまり私=母親=世界なんですね。
ところがあるとき、母親から引き剥がされてしまうことが発生する。母親が不在になってしまうことがある。
そのときっていうのはまさしく世界の危機ですよね、この子にとっては。
ここらへんの細々したところはややこしいので触れませんが、母親と引き剥がされた子どもが、母親を呼び止めるために必要となるのが、言語です。
「ママ」っていう言葉です。
それによって、母親が取り戻せるかもしれない。
ただ、ここで言語が介入することで、この子にとっては大きな出来事が起きるんですね。「ママ」と呼びかける対象ができたってことは、同一化していた母親との間に線が引かれたってことですね。
さらに、「ママ」という呼び名が発生した瞬間に、母親は母親そのものではなく、「ママ」という言葉を通した存在っていうふうに姿を変えてしまうんですね。
さらにラカンの重要な概念に「鏡像段階」っていうのがあるんですが、赤ん坊が鏡の中に映っている自己像を自分の姿であると認識することをいいます。この鏡像段階で「私」というものに出会ってしまった子どもは強い衝撃を受けるわけです。
母親と自分が違った存在である。
世界の中に「私」が存在してしまっている。
言語の介入によって「ママ」という言葉(見方)を通してしか母親に触れることができない。
このようなことを起点にして発達がはじまります。
ヴィゴツキーが言ったように、言語は他者の言葉=外から内にやってきます。たくさんの人の思考によって織り上げられた言語規則が、子どもの思考や物事の見方を規定するようになります。
ラカンは、介入してきた言語によって織り上げられた世界のことを「象徴界」と呼び、また「大文字の他者」とも呼びました。つまり絶対的な他者ということです。
わたしたちは、目の前の世界をそのまま現実だと思って過ごしてますけど、実はちがうんですね。
言葉によって、つまり象徴界によって切り分けられて、秩序づけられた後の現実っていうのを見てるんです。
それをラカンは「想像界」っていいました。いま話題の仮想現実的なイメージですかね。
映画のマトリックスで、キアヌ・リーブスたちが闘ってた世界が想像界で、緑色のプログラムコードがワーッて降ってくるみたいなシーン、あれが象徴界です。
象徴界によってコーディングされた想像界っていうのを人は生きてる、ってラカンは考えたんですね。
もうひとつ現実界ってのもあるんですけど、それは言葉を持ってしまった人には触れられない領域であるっていうふうにしました。
これ以上ラカンについて触れるといよいよ迷子になってしまうので、そろそろ終わりにしますが。
言いたかったのは、子どもが言葉を獲得するそのはじまりのときに、言語によって規定された現実っていう中にいつのまにか投げ出されてしまってるんですね。
目に見えている世界の裏側に、それをプログラムしているコードがある。
さっきも話した、規則によって見方や思考が規定されるっていうのが、またここでも出てきました。
ただ、面白いのは、そういう規則、つまり言葉のルールとかって、とくに母国語の場合は、頑張って勉強して覚えたってわけではないですよね?
なんとなく、この言葉はこんな意味だなって、使えるようになっていきましたよね。
ここでさっき言ったウィトゲンシュタインって人がまた出てくるんですけど、この人が「言語ゲーム」っていう概念を考えたんですね。
「語の意味とはその使用である」っていう言葉は、この言語ゲームについての考察から出てきたんです。
たとえばゲームって、サッカーでも将棋でも花いちもんめでも、それぞれにルールがありますよね。で、プレイヤーはそのゲームのルールに従って動くわけです。
たとえばサッカーをしている少年たちを遠くから見てるっていう状況を思い浮かべてください。
しばらく見てたら、急に誰かが、ボールを手でつかんで走り始めたら、「え、ラグビー?」ってなりますよね。でも、子どもたちは楽しそうに続けている。
って思ったら、今度はそのボールを人に当てて周りは逃げるみたいな「ボール当て鬼ごっこ」になってたと。
それも横から見てる人は困惑しますよね。なんのゲームをやってるのと。
でも子どもたちは、戸惑いもなく遊びまわってる。
プレイヤーの子どもたちは、他のプレイヤーの振る舞いとかを見て、なんとなくルールを掴めているんですね。
外から見て客観的に勉強しようとしたら、実はそっちの方が難しかったと。
この事例をそのまま言語に応用すると、言語ゲームの考え方になります。
ある集団があって、そこではある種のルールによって語の使い方が決まっていると。
「りんご」っていう言葉が何度も出てきて、遅れてきたプレイヤー(幼児)は、その「りんご」の使われ方を見て、自分も使ってみる。
周りが特に変な反応を示さないなら、その使い方はオッケーってことですね。
そうやって語を獲得していくと。
で、それぞれの集団によっては全部ルールが違う、つまり使い方が違ったりする。
ゲームとゲームの間には「家族的類似性」っていうのがあって、「どこがとかじゃないけど皆なんとなく似てるよね」、っていう家族の顔が似てるよねっていうのが家族的類似性ですけど、そんなふうな仕方で言語ゲーム間、集団間でルールに類似性があると。
だから、他の集団で使用した「りんご」をここでも使うことができる。
それで周りの反応が大丈夫であればオッケー、っていうことですね。
だから全部言語ゲームなんだ、っていうふうにウィトゲンシュタインは言ってるわけですね。
りんごに意味があるんじゃなくて、どう使われてるかを体得するのが、言葉の意味を知るってことだよと。
成長して、言語をうまく話せるようになってきてはじめて、「これは〇〇って意味だよ」っていう教え方でも理解できるようになるんですね。
だから、例えば英語と日本語とか、子どもが2つの言語を一気に覚えるのと、母語を習得した後に第2言語を習得しようとするのは、まったく別のプログラムなんですね。
これに関してはみなさんなんとなく解ってらっしゃるとは思うんですが。
園でも、僕が担当して「こくご」の時間っていうのをやってるんですけど、上のクラスは劇をよくやってます。
即興だったり台本使ったりもしますけど、即興の場合は日常的なシーンで、例えば親子で買い物とか、食事とか、子どもにとっては、お父さんお母さんとか他者が使う言葉を喋れるような言語ゲームの場にしたいと思っています。
BCグループは、まだ劇とかには入れないんですけど、最近は大きい小さいっていう言葉を使ってレッスンをしました。
特に面白かったのは、Lちゃんは純粋なアメリカ人なんですが日本語ちょっとずつ上手になってきてるんですね。
ただ、大きいと小さいについてはわかんなかった。でも実物やカードを2つ使って「大きいのはどれ?」とか「小さいのどれ?」とかを、他の子も一緒にやってたら、後半はLちゃん個人的に質問しても、ちゃんと応えられるようになってました。
こういうのを見ると、「なるほど、意味とはその使用だな」っていうのがなんとなくわかるような気がします。