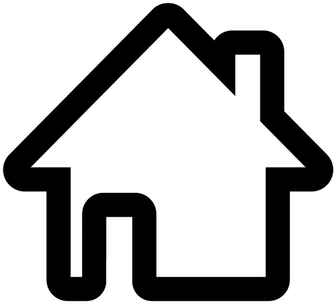さて、いよいよ、仮説3である。お待たせしました。
はて、誰がこれを、お待ちしていたのだろうか。
うるさい。そんなことは関係ない。誰が読むとかは関係ねー。俺が書きてーんだ!それが一番大事なんだ!それ以外なんにもいらねーんだよ!
てな感じでかっこいい啖呵を切ってみたいではありますが、でも結局読まれたいよねー。
1日のPV数5000万とかなってアフィリエイトとかで生活とかしたいよねー、あとはしれっと一時期流行ったステマブログ的な感じでちゃちゃっと稼ぎたいよねー。
まあ別に手段とかは問わないというかなんでもいいからさ、お金欲しいよねー、というかもうちっと詳しくいうと、働きたくないよねー、働かないままに生きていきたいよねー、蛇口ひねればジュースとか出てきてー、頭とかガリガリ掻いたときに出てくるフケが実は美味でしかも栄養価もバリ高いみたいな奇跡が起こればいいのに。ほんと。
さて、本線に乗る前に脱線してしまいました。それははたして脱線と呼びうるのかという問題はそのままにしていきたいと思います。
仮説3_琉球舞踊とは、濃縮還元である。
(仮説1_琉舞とはプログラミングである(真っ白な腕と片足立ち))
(仮説2_舞台上の時空は歪んでいる(特殊相対性理論的な))
わたしって、ファミレスが好きじゃないですか。で、ドリンクバーとかよく注文するじゃないですか。注文するんですよ。
で、やっぱり元を取りたいっていう心理がはたらくもんだから、お腹タプタプになるくらい、誰かに腹部を圧迫されたらプシューって口から水分吹きますみたいな、「オス!オラ、マーライオン!」みたいな感じになること瞭然なくらいに飲んじゃうのです、ジュースを。
居酒屋より、ファミレス行きたいよねほんとは。
今度から、カクテルをカラコロ作るバーよりも、機械でドワーッってやるドリンクバーにしません?
ってこれは誰に向けた言葉なのかな?
まあいいや。ちなみに、この文章もドリンクバーのあるファミレスで書き書きしているわけで、って考えたら、お金もらうどころか減ってるじゃん!なんなんだよ!領収書切るよ?いいの?アテナどうしたらいい?
はぁ、本線に乗るのはなかなか難しいのですね。
濃縮還元ってあるじゃないですか。
100%オレンジジュースとかで、「濃縮還元」って書かれてるやつは、オレンジを絞ったやつそのまんま(ストレート)というわけではなくて、一度水分を飛ばして粉状にするなりペースト状にするなりして濃度を高めた上で、後で水分を加えて濃度を戻すってことをやってるわけですね。
ファミレスのドリンクバーのジュースたちは、濃度の高い液体を、注ぐ時に水と混ぜて濃度を戻すってなことをやってる、この濃縮還元のやつなわけですね。
グラスを置いて、ボタンをピッてしたら、ジャーってなって、濃度高めの汁と水とが両方ドボドボ出てきて、グラスの中で混ざってちょうどよくなる、みたいな。
でもたまに、おいおい、これ色がついたただの水じゃん、みたいな。
さて、この濃縮還元が、琉球舞踊とどのような関係があるのでしょうか。
言い方を変えます。
ここからどうやってこじつけるのでしょうか。
つまり、これからわたしはどうすればいいのでしょうか。困ってます。
今回の『蓬莱2』と、前回公演『蓬莱』(便宜上、この後は『蓬莱1』と記します)のちがいは、もちろん演目もちがうんですけど、前回は一番はじめ(第一部)にあった素踊りが、今回は一番最後(第三部)になっていたんですね。
そのちがいのせいか、前回は気づかなかったのだけど、今回はっきりとわかったことがありました。
それは、踊り手が「汗をかいている」ということです。
やっと本線入ったと思ったらソッコーで結論めいたことを書いてしまうという。
それならスッと書けや!という文句を垂れる人がもしいたとしたら、その人はわたしにドリンクバーの料金くらい立て替えてから言ってください。
まあ、どうせいないでしょうけど。
そもそも読者もあまりいないのだし。
「汗」について、じゃあ、書いていきます。
「素踊り」ってのは、琉舞の踊り手たちが、化粧をせずに素顔のままで披露する踊りです。基本琉舞は真っ白に化粧を施して踊るわけですが、スッピンを晒しちゃうわけですね。もしかしたらちょっとはメイクしているのかもしれませんが、インスタとかでよくやられてる「すっぴんメイク」的な。
『蓬莱1』についての記事のなかで、(コチラ)
(『蓬莱1』:仮説4_「蓬莱」における「素踊り」は、「革命」を志向する行為である)
と書きました。
加えて、『蓬莱2』の仮説1では、「完璧に設計された(プログラミングされた)動きが、琉舞の理想である」ということも書きました。
個人を隠蔽し、同質化し、機械化する、このようなラディカルな指向性を琉舞はもっていたと考えることができます。
そのようなベクトルに対する、ある種の「抵抗」あるいは「革命」として、「素踊り」があるのではないか、というのが、『蓬莱1』における仮説4(「蓬莱」における「素踊り」は、「革命」を志向する行為である)の論旨でした。
素踊りによって、王府の目指そうとする、踊り手たちの「没個性化」「同質化」「機械化」というものから逃れる、あるいは立ち向かう。
それってつまり、「人間性」の確保や回復を願っての行為だといえると思う。
その「人間性」っていうものを、前回(蓬莱1)の記事においては、「化粧をしないこと」によって回復しようとしているとした。
でもそれだと、ネガティブな形式での存在証明にしかなり得ない。
つまり、自分が「没個性的・同質的・機械的では“ない”」ことの告白によってしか人間であることを立証できないということである。
「わたしは機械ではない、だから、人間である」というふうにしか、これでは語ることができない。
踊り手たちは、「ない」ことではなく、「ある」ことによって自らの「人間性」を担保したい。
そこで、「汗」である。言い換えると「水分」である。
プログラミングで設計された機械にはなくて、人間にはあるもの。
アンドロイドにはできなくて、人間にはできること。
それは、「汗をかくこと」である。
第三部の素踊りの際、踊り手たちの額や首筋には、うっすらと、でもはっきりと、汗が滲んでいた。
光を反射し、煌めいていた。
水分を含むか含まないか。
そこに、人間と機械との境界線が引かれるんじゃないか、そんなことを思わされた。
琉球舞踊は、オレンジを絞った果汁から水分を抜き取って粉末にするみたいに、美学や芸術性をその形式性に濃縮して保存期間を延長してきた。
「伝統」として、保存され、代々受け継がれてきた。
琉舞を琉舞たらしめる、真っ白な化粧、華美な衣装、完全なる「型」(プログラム)、それらはすべて、その「伝統」をできるだけクラシカルな形で再現するために必要な装置である。
つまり、抽出して濃度を高めた「伝統」に、踊り手=水を加えることで「搾りたて」の状態に戻すというわけだ。
そのためには水の量や質が、とても重要になってくる。
量を間違えれば味が濃くなったり薄くなったりするし、蒸留水か自然水か、あるいは硬水か軟水か、によっても味わいは変わってくる。
どんなに「伝統」の抽出度を高めても、それを戻す(演じる)踊り手によって味は揺らいでしまう。
だからこそ、水の質や量を一定に保つ必要がある。
その品質管理を徹底するために、踊り手の「没個性化」「同質化」「機械化」を目指そうとするわけだ。
でも、踊り手たちをいかに機械に近づけたとしても、拭っても拭っても拭いきれないのが、「汗」。
このことを、第三部の素踊りで化粧を落とすことによって、踊り手たちは暴露した。
「汗」こそが、踊り手を人間たらしめる、機械化への抗いのための唯一の装置なのである。
この「汗」によって、踊り手は、否定による存在立証から脱却することができる。
「わたしは機械ではない、だから、人間である」ではなく、「わたしは汗をかく、だから、人間である」という語りを獲得することができる。
人間と機械の境目、それは、汗をかくかどうか。
汗をかくということは、人間であることの証明である。
であるなら、隣の奴が汗臭くても、それに嫌な顔なんてしないで、ああこの人はちゃんと人間らしくいるのだなあと思ってほしい。
思わなくてもいいけど、嫌な顔はしないでほしい。
もし嫌なら、しれっと遠ざかってほしい。
お願いだから、そうしてほしい。
だって、気にしちゃうのです、わたし。
アイウォンチュー、シーブリーズ。