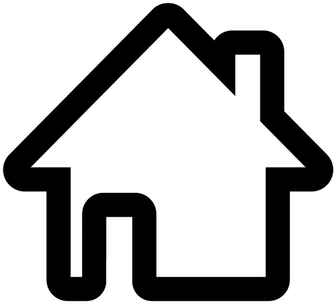去年、『「蓬莱」に関するいくつかの仮説』という記事を書いたんですけれども(こちら)、4月7日(土)に、2度目の公演があったのでした。
またしても悪友・玉城氏が出ているので、観に行ってきたのですが、いろいろと新たな仮説が浮かび上がってきたのでございました。
というわけで、今回もまた、無責任なことをダラダラと書いてみようと思うのであります。
仮説1_琉舞とはプログラミングである(真っ白な腕と片足立ち)
(仮説2_舞台上の時空は歪んでいる(特殊相対性理論的な))
(仮説3_琉球舞踊とは、濃縮還元である)
第1部の創作舞踊「春曉」において、踊り手達は紫紺の着物をまとっていた。
それはとても美しくて、踊り手が動き、布が揺れ、その度シワの部分の色が濃くなったり淡くなったり移ろっていて、そのグラデーションにとてもうっとりとさせられた。
その綺麗な布のその袖から、真っ白な腕が生えている。紫と白のコントラストが、さらに美しさを助長していた。
なーんつって書いていますけども、実際のところわたしは、衣装の美しさよりも腕についた白粉のことがずっと気になっていたのでございます。
どういうことかっていうと、袖に、それから持っている扇子に、白い粉がついちゃうんじゃねーだろーか、ということです。汚れちゃうよーなんて、余計な老婆心を抱いてしまっていたのです。集中せい!というやつです。
でもね。やっぱ気になっちゃうものは気になっちゃうので、ずっと腕の白粉ばっか見てたんです。
すると、あることに気づいた。
顔や首元や手の甲はそうじゃないんだけど、手のひらに施した化粧だけは、踊り手によって濃さが違うんです。
なぜか。
まあ、特に理由はないんだろうと思います。踊りのなかで扇子や袖を持つことが多いから、踊り手個人の塩梅で調整しているのでしょう。
でも、無責任な観客であるわたしは、そこにいちいち意味を見出して偉そうにしたいのです。たとえそれが、悪ふざけな論であったとしても。
以前の記事で、こんなヘンチクリンなことを書きました。
イメージとしては、動画ではなく、連続写真のような感じ。
膨大な量の、極度に細分化された「型」に身体を当てはめ、それを見ているわれわれ観客には「動いているように見える」、というような見立てで持って琉舞を見ることが可能なんじゃないか、と思ったわけであります。
この仮説を延長させて考えていくと、「プログラム」の概念で琉舞を見ることも可能なんじゃないかと思ったのです。
つまり、完璧に設計された(プログラミングされた)動きが、琉舞の理想である、という見立てです。
もちろん人間が踊っている以上そんなことはできないわけですが、極度に細分化されたひとつひとつの所作(型)をデジタル信号として組み込んだアンドロイドがもし存在したとしたら、踊り手達と同じ動きを実現することが可能なんじゃないだろうかと思ったのです。
でも、誤解のないように書いておきますが、これは、踊り手は機械化できるとか、何も考えずに踊っているとか、そういうことを言いたいのではありません。
そうではなくて、舞踊家たちはそれほどまでの膨大で細やかな所作を要求されるストイシズムな存在だということです。
そのことが表されているように感じたのは、舞踊のなかで多発される「片足立ち」です。
これまで(少しだけですが)見てきた舞踊と比べて、この「春暁」のフリにはやけに片足立ちが多いような印象を持ちました。
片足立ちって、速いテンポの中では特に気になりませんが、スローな流れの中で課されると、バランスを保つのが難しいし、見る側もその「ゆらぎ」や「ふるえ」などから不安定な印象を抱いてしまいます。
でも、「春暁」のなかではこの「片足立ち」をなんども求められる。
化粧によって素顔が隠蔽されていたり、着物によってシルエットがぼかされている踊り手たちですが、実装されたプログラムの実行(片足立ち)とその反復によって、アスリートな身体性が浮かび上がってくるのです。
という論をここで大きく飛躍させて、踊り手たちは、機械の身体を実装しているという見立てを採用します。
ひらたくいうと、彼らはアンドロイドであるとします。
以前の記事にもかきましたけど、(コチラ)わたくし最近、『ブレードランナー』にかぶれておりまして、アンドロイドのことをよく考えるのです。
で、そのときに絶対に考えざるを得ない論点というのが、「機械と人間の境界」ってことなんです。
で、先ほど述べた、手のひらの白粉についてです。
踊り手たちは、顔や首元はもちろん、腕や手の甲にもしっかりと化粧を施していました。
でも、手のひらだけはその濃さがちがっていたのでした。
手のひらと手の甲の白さの「差」、そこに、機械と人間の境界があるのではないか、と思ったのです!
(何を言っているんだお前は!と思っている方へ。私もそう思います)
ここで無理やりメチャクチャなロジックを組み立てると、手のひらの化粧が濃いほど、言い換えると手のひらと甲の白さの差異が小さいほど、その人は自らのアンドロイド性を強く自覚しているということです。
逆に言えば、手のひらの化粧が薄い人は、アンドロイドと人間の狭間でアイデンティティの「ゆらぎ」を覚えているということです。
6名の中で、わたしから見て、もっとも手のひらの化粧が濃かったのは、阿嘉さんでした。つまり、阿嘉さんはアンドロイドなのでした。
さて、阿嘉さんがアンドロイドであるということが判明したところで(阿嘉様、まったく面識がないのに適当なことばっかり書いててすみません)、踊り手が「プログラミング」されていることを裏付ける(と勝手に捉えきれる)もうひとつの要素が、「太鼓の不在」です。
音楽の途中で、それまで鳴り響いていた太鼓が鳴り止む瞬間がありました。
もちろん、他の音楽の中にも太鼓の音がなくて三線や琴や胡弓の音のみで構成されたものもあったのですが、そうではなくて、急に太鼓の音が消失した瞬間があったのです(わたしにはそう感じました)。
これはどういうことかというと、「ビートが消えた」ということです。
普通、太鼓によって刻まれているビートを目安にして身体運用はなされるものだと思います。
ですが、その目安が突然失われたのです。舞台上にはメロディだけが残った。
つまり踊り手たちは、踊りの途中で、ビートに乗せた身体モードからメロディに乗せたそれに瞬時にスイッチしたわけです。こんなの、機械じゃないとできません(って言ってみたかった)。
と、長々と書いてきましたが、まだあといくつか思いついた(「見つけた」ではないことに注意)仮説がありますので、それは後々書く予定です。
とりあえずこのあたりで仮説1はヤメておきます。
踊り手がアンドロイドだどうだとかってフザけたことを書いてきたわけでありますが、つまりですね、みなさんの日々の鍛錬に畏敬の念を抱いているというわけであります。いつも稽古お疲れさまです。
(こうやって媚びておけばなにか良いことがあるんじゃないかとかは別に全然、思ったりとかはしてないです)