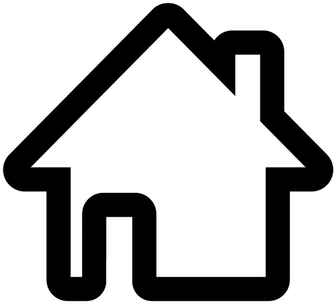どうも、兼島です。
このたび、わたくし兼島の書いた脚本「私たちの空」が、第13回おきなわ文学賞《シナリオ・戯曲部門》を受賞(佳作)しましたー!
みなさま、めでたいことですので、ぜひお祝い金を握りしめてワタクシ兼島の家までお越しください。
おもてなしはできませんが、現金だけは確かに受け取らせていただきます。

「かりゆし・かりゆし 〜恋するシーサー〜」
と、いう沖縄芝居(ミュージカル?)を観てきました。
うん!面白い!これはいいね!
子ども達にもわかりやすいし、しまくとぅばやうちなーぐちがわからなくても全然楽しめる(現代日本語も多用される)。
しかも、ただわかりやすくしているだけじゃなく、ちゃんと批評的というか、「わかりやすさ」に対する自問自答も内包している。
会話やストーリーも、歌や踊りも、エンタメ的にとても優れているし、琉球芸能への入り口としてとても間口の広い、オープンでウェルカムな作品になっていると思った。
と、わかりやすい感想をここまで述べたので、ここから先はわかりにくい、粘っこくて回りくどい、複雑でややこしいことを書いていくことになると思われます。
この劇ってのは、もう人も住まなくなった島に残された1組のシーサー夫婦のお話です。彼らは300年にもわたり、民家の屋根の上で寄り添って暮らしてきました。
お互いにチクチク小言を言い合って、各々が、過去に恋い焦がれた相手(人間)のことを想像し、あの頃に戻れたらとかあのときもしも・・・とかって寂しさを感じつつも、最終的に夫婦の関係性を見つめ直しお互いに信頼を確かめ合う、みたいなストーリーです。
それを、歌やダンスや会話でやっていくってわけです。
そんなあらすじ。
登場するのは、シーサー夫婦と人間の男女。それを二人の役者、玉城匠さんと小嶺和佳子さんが演じておって(ちなみに匠くんはアタイの同級生かつ野球部の同士だよん)。
だからシーサーをやってたと思ったら、いつのまにか早着替えをして今度は人間の役をやっておる、みたいな感じね。忙しい!
んで、ここがポイントなんですが、シーサーの夫役は女性の役者(小嶺さん)が、妻役は男性の役者(匠くん)がそれぞれ演じていたわけです。
大事なことなのでもう一度書きます。
夫役を女性が、妻役を男性が演じていた。
なぜここがポイントなのかは後々回りくどく説明します。
ちなみに、人間の男女に関しては、それぞれ男役は匠くん、女役は小嶺さんでありました。
つまり、シーサーは、男女の性が反転されているわけであります。
これって、えっとどういうこと? なんて考えておりました。
劇中、シーサーの夫婦は基本軽めに口喧嘩をしているわけであります。
んで、「なんであんたとなんか一緒になんなきゃいけなかったのよ!しかも300年も!」的な言葉をお互いに投げ続けるわけですね。
そこでどっちか(たぶん夫)が、「俺に文句言うな、シーサー職人の気まぐれでこうなっちゃったんだから!」みたいな、ね、そんなことを言っちゃうわけです。
そこですかさず妻が、「あー、ダンディなあの殿方、いまごろ何をしてらっしゃるのかしら?」みたいなモードに突入。で、音楽ドーン!早着替えスーン!という展開がありました。
実は、いま書いたところがキーなんですね(どこだよ!)
「シーサー職人の気まぐれでこうなっちゃったんだから!」的な言葉ですね。
この言葉で示されているのは2点。
1つは、彼らシーサー夫婦が、人間の手による人工物であるということ。
もう1つは、彼らの意志とは関係のないところで、夫婦であることを強制的に決められたということ。
この「強制性」こそが、二人の諍いの根本にあるんですね。そこに、人工物であるのに「感情」を持ってしまったことで、いよいよ関係の悪化が表面化してきてしまった。「なんでお前なんだよ!」って。
突然ですが、『ブレードランナー(オリジナル)』および『ブレードランナー2049(続編)』っていう映画は、強制的な隷属状態に置かれたレプリカント(人造人間)が、人間と同じように感情を持っていて、自らを作り出した存在=人間に反旗を翻すっていう設定が物語を駆動するエンジンになっています。
んで、特に、『2049』のなかで「奇跡」って言葉が何度か出てくるんですね。
あるレプリカントが、自身を殺そうとする主人公(こいつもレプリカントなんだけど)に「お前は「奇跡」を見たことがないからだ」みたいな言葉を言って非難するわけなんですけれども、この「奇跡」ってのは、「出産」のことなんです。
被造物であるはずのレプリカントが、新しい命を生み出す。その「奇跡」を目の当たりにしたレプリカントたちが力を受けて、革命を志すわけです。
一人のレプリカント=人間の誕生が、活力を多くの人々に授ける。「新たな命を生み出す」というのは、それほどに大きな、潜在的な力を秘めている。
シーサー夫婦がレプリカントと違うのは、屋根の上に固定されて、自由に動くことができないということです。これって、ひどく残酷な設定なんですよね、シーサーにとっては。
しかも畳み掛けるように、メタレベルを一つ上げたところ、つまり役者レベルで見ると、男女性が反転して配置されることで、子どもを産むための男女双方の役割が不能化されて描かれてしまっているのです。
屋根の上以外からどこへも行けないという不自由さ。夫婦でありながら、子どもを持つ可能性を最初から排除された不自由さ。
このシーサー夫婦は、シーサー職人と演出家の手によって、強制的に「力」と「力が生まれる可能性」を奪われてしまっているわけです。
じゃあこのシーサー夫婦にとって、彼らの人生は悲劇なのか。というと、そうとも言えない。先述したように、彼らは最終的に、お互いの大切さを確かめ合い、共に生きていくことを誓い合います(300年も一緒にいるんだから、何百回もこんなことがあったのでしょうが)。
ここに「家族」という可能性が秘められているのです。
哲学者の東浩紀さんという方が書いた『ゲンロン0』というべらぼうに面白い本のなかで、「家族の哲学」という論考があります。
そのなかで、家族を「強制性・偶然性・拡張性」というポイントでもって論じます。
「家族」というコミュニティは、自由意志で出たり入ったりできるものではありません。とくに子どもにとっては、望む望まないに関わらず、その家族のあり方からは自由にはなれないのです。そういった意味で「強制」的である。
でもって、家族は「偶然」の産物でもあります。たとえば親と子の間には、偶然が大きく作用しています。「私」がこうして存在するのは、「私」の特徴を備えた精子と卵が結合したからであり、それはまったくもって「偶然」なわけです。親は子を「選ぶことができない」わけです。
親子だけでなくて、夫婦(男女)の出会いにおいてもそうで、ミクロな視点で見るとそりゃ「この人だ!」って決断して結婚したわけなので必然なのですが、でもマクロに見ると、そもそもの出会いの時点で、双方の地理的および時間的な条件などの偶然的要素に完全に左右されているわけです。
そしてもうひとつ、家族は「拡張性」をもちます。当たり前ですけど、夫婦と子ども(核家族)だけの形態が家族なのではありません。祖父母や伯父伯母叔父叔母などと共に暮らすこともあるだろうし、たとえば「里親」や「養子縁組」などの制度によって、あるいはなぜか父の友人が居座ったりして、血の繋がりのない存在が入ってくる可能性もあります。また、犬や猫などの動物や、アイボなどのロボットすら加入する余地があります。
こんなような「拡張性」によって血も種も超えてつながれる、それほど恣意的なものでもあるわけです、家族って。
またしても『2049』の話になるんですが、主人公”K”は、さっきもちょろっとだけ書きましたがレプリカントなんです。んで、その恋人”ジョイ”は、AI(人工知能)です。ジョイにいたっては、肉体を持たず、空間モニターに表示されているだけの、いわばイメージです。
その二人の人工物、プログラムされた存在同士の恋愛が、この映画の重要なテーマを描いているのです。
つまり、「愛とは何か?」ということです。プログラムされた「愛」は、本物の「愛」と呼びうるのか? みたいな。
Kとジョイの間に育まれた大切な「愛」は、データの破壊によっていとも簡単に消え去ってしまいます。そこに悲しさがあるのですが、これ以上語るとあれなのでもう映画を見てください。
また戻ってきて、シーサー夫婦は、強制的に夫婦として生み出された存在(人工物)です。それでもって、完全なる偶然(職人の気まぐれ)によって二人は出会ったわけです。そこに互いの意志が介入していないからこそ、彼らはいがみ合うわけです。俺だって、私だって、恋がしたいんだ!って。
彼らにはいまのところ破局の可能性はありません。ずっと屋根の上から動けないから。でも、二人は「愛」でつながっているわけでもありません。「偶然性」と「強制性」によって接続され、接続され続けているのです。
でもこの劇が描くのは、その先のことです。
つまり「偶然」と「強制」によってできあがったこの関係を超えて、見せかけのものでしかなかった「夫婦」という関係を超えて、ほんものの「家族」になる。そういうお話なのです。
ふたりの間に「愛(恋愛感情という意味での愛)」はプログラムされていなくても、また、子を生むという可能性を奪われていながらも、ずっと長い時間をともに過ごしてきたという「情け」や「慈しみ」によってそれを乗り越えて(拡張して)、「家族」を形成することができる。ここに大いなる希望が描かれています。
公演タイトルにもある「かりゆし」という言葉。作・演出の嘉数さんは創作ノートの中でこの言葉を、「めでたい」とも「HAPPY」とも違うニュアンスであり、訳することができないと述べている。
これまで書いてきた「家族」についてのことを振り返ってこの「かりゆし」という言葉を考えると、「めでたい」とか「しあわせ」とかという「実感」としての意味合いにプラスして、「慈しみ」や「情け」など他者へ宛てた「想い」も含まれた言葉なのかなーなんて。
このような「かりゆし」という言葉(概念)を背景にして、「ゆいまーる」などといった、たまたま同じ地域で過ごしている人たちの(偶然性)、血縁を超えたしなやかな関係性の構築(拡張性)が可能になるのかなーなんて。思ったり。
でも、そういう「慈しみ」や「情け」とかによる関係構築って、ある意味費用対効果が悪いんですよね。だって、わざわざコミュニケーションの負荷が増えるし、それをしたからって自分の利益には直接繋がらないことも多い。
でも、「でもやるんだよ!」ってことを叫びたい。叫びたいんだけど、でもそれを、わたしたちはいつまで叫ぶことができるでしょうか。「面倒だから、やーめた」って、「慈しみ」も「情け」も切り捨てた効率的な生き方を、いつ志向するかもわからない。そうなってしまうことへの恐れってのは、これからの時代、ずっと付きまとってくるものなんでしょう。
劇の最後、シーサーの妻が、現代日本語を話す理由を夫に問われ、「便利だから」と答えつつ「でも、便利だからってこのままでいいんですかねぇ。。。でも、仕方ないんだけどねえ。。。」みたいな自問自答を呟いて物語は終わります。このセリフは演じている役者自身を相対化したメタレベルでのものであると同時に、演劇や琉球芸能全体に向けたメタ・メタレベルでの問いかけでもあります。さらに、ますます加速していくグローバル資本主義にのまれた現代社会へのメタ・メタ・メタな自問でもある。
こんな時代の中で「恋」とか「愛」とか「慈しみ」とか「情け」とか、そういうのってなんか軽く扱われちゃってるような気がしてるんだが、「めでたい」とか「しあわせ」とかをも包み込んだ「かりゆし」を実現するためにも、そういう「”効率の悪い”感情」というものを愛でる姿勢を大切にしていかなきゃな。
それができるのって、もはや芸術と宗教くらいなんじゃないか。
というわけなので、これから、宗教団体をつくろうかと。。。ちがうか。

腐れ縁の匠くんとワタクシ。シーサーポーズがかわいいね。