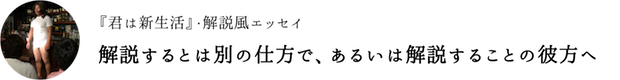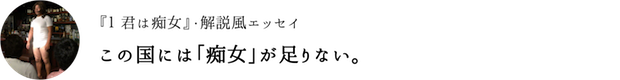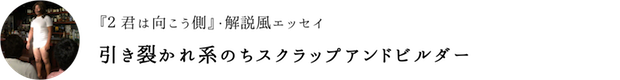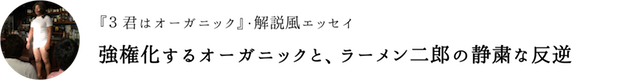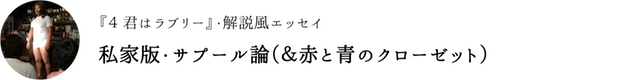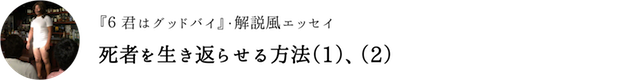死者を生き返らせる方法(1)、(2)
(1)
部屋で、ひとりぼっちでぼーっとしてるとき、ふと、不安になることがある。
いまもし、心臓発作とか脳出血とかまあその他の緊急的なアレで死んじゃったとしたら、誰か、僕を見つけてくれるだろうか?っていうようなことを思う。
ずっと、誰にも知られないままは嫌だなあって思う。
四方の壁と天井と床。その囲われた空間の中で僕は寝て起きて食べて本を読んでまた寝る。
その囲われた空間にいるとき、その空間の外側、つまり「世界」との間に断絶が生まれる。部屋にいるとき、僕は「世界」に「存在」していない。僕がいまいるこの部屋は、「世界」とは明確に区切られている。
存在感、って言葉がある。これがよくわからない。
存在感があるっていうのは、どういう意味だろう? 目立つってことだろうか?
存在している感。「感」。そうか、「感」が大事なんだ。……と、なんとなく思った。
ある人の存在感がもっとも際立つのは、逆説的だが、その人が「不在」のときだと思っている。
人や物や、あとなんでもそうだけど、「失ってその大切さに気づく」なんて言葉をよく聞く。J-ポップっぽい言葉。
その言葉にはたいてい「だから、いま当たり前に目の前にある人(や物)をちゃんと大切にするんだよ」っていうようなメッセージが続く。そう言わなくても、そのような意味がほぼほぼ含まれている。
でももしかして、「失ってからしか気付けない」という普遍(不変)のシステムが人間の中にプログラミングされているんじゃないか。
京都大学総長の山極寿一さんは、人間と類人猿とを分かつものは、「不在の認識」だという。
ゴリラやチンパンジーの群れは、基本的に、誰か仲間がいなくなった場合、その仲間を「いなかった」ヤツとして集団生活を継続する。「不在」の者の「空席」をつくっておかない。
でも人間は、「不在」の者を、ちゃんと認識する。
「いるはずなのにいない」者として捉え、その「いるはずなのにいない」者を勘定に入れて集団を運営していく。
そのとき「いるはずなのにいない」者は、同時に、「いないはずなのにいる」者でもある。
その場に「不在」であるのに、そこに集う人たちが示し合わせて、その「不在」の者を「存在」しているふうに装う。
誰かが「不在」の空間のなかで、その「不在」を共同幻想的な「存在」としてつくりなおすことができること、これが人間の人間たる所以である。
であるなら、その「不在」を出発点とする関係性の構築方法こそが、人間の根源に宿るものなのではないだろうか。
僕らは、会わなくなった人、いなくなった人に、想いを馳せることができる。
あの人はいまごろ、何をしているだろうか? なにを考えているだろうか?
先日、うるま市で起きた、米軍属の男性による強姦致死事件。あの事件は、本当にいろんな面で強烈な打撃を受けた。
あの被害者の女性は、どういうことを思いながら、亡くなっていったのか。やっぱり、怖くて、苦しくて、悔しくて、無念だったのだろうか。
犯行の醜悪さ、被害者女性へのやりきれない想い、家族や恋人や友人たちの無念さ、凶悪事件が身近で発生したことの恐怖。それらを想像する。すればするほど、僕は自分の頭の中がグチャグチャになって、もうワケわかんなくなっていった。
テレビをつけると、さまざまな色の旗を掲げて感情を噴出させて反基地運動をするたくさんの人が、画面の奥にひしめいている。
スマホ画面に目を移すと、その反基地運動への反発や違和感を表明する言説がどんどんスライドしていく。
あの事件を前にして、何を想うのが「正解」だったのだろうか。
僕は、ただオロオロするしかできなかった。僕はただの傍観者だった。傍観者として、事件の相貌に絶句し、身体を硬直させることしかできなかった。
抗議をする群衆の中に入っていくことも、その抗議に抗議をするような投稿をすることも、どちらもできなかった。どうすればいいのかわからなかった。
僕は、傍観者である自分に、少し嫌気が差していた。
あの被害者の女性は、こんな僕を見て、なにを感じただろうか。それを聞いてみたいと思った。
いや、もちろん、僕と彼女との間に面識はない。事件のことと同時に彼女の存在を知った。
だから彼女も僕のことを知らないし、僕のことを考えることなんて関係性的に有り得ないだろう。
それにもちろん、亡くなった彼女にそれを聞くなんてことは物理的に不可能だ。
でも、それでも彼女に聞きたいと思った。僕のような、傍観者である人間のことをどう思うのかを。
僕は、そのとき、彼女の言葉になにかを期待していたのだろうか。
「オロオロ」している僕に、「こうしたらいいよ」って「正解」を教えてくれることを待っていたのだろうか。あるいは、その「オロオロ」に嫌悪感を抱いていた自分を、慰めて欲しかったのだろうか。「気にしなくていいよ」って、言って欲しかったのだろうか。
どっちだろうか。どっちもかもしれない。どっちでもないかもしれない。
正直わからない。
でも僕は、どちらにしても、どちらでもないにしても、彼女を「呼び出そう」とした。
呼び出して、その「声を聴こう」とした。あえて引っかかる言葉で言うと、僕は彼女を「利用」しようとした。
彼女の死は、沖縄中にたくさんの議論と運動を生んだ。
彼女のことを知らなかったたくさんの人たちが、「不在」の彼女を呼び寄せて、つまり「存在」させて、自らの隣の「空席」に座らせた。
それがどのような想いや言説であっても、それを語る彼らの意志によって彼女は「存在」させられた。
生者の声によって「死者」である彼女は何度も生き返らされた。それはまぎれもない事実だ。
それは「昇華」への意志でありながら、一方では「暴力」でもある。
そのことを、あの事件や彼女のことを語る人間は宿命として背負わなければならない。
「利用している」と言われても、それを受け入れなければならない。
これが、僕がたどり着いた一応の「答え」。
この「答え」が何か問題を解決してくれるわけではない。状況を好転させる策を見出すことはできない。
でも僕は個人的にしばらくは、この「答え」に従おうと思う。
尊い命が失われたとき、その「死者」に想いを馳せるとき、僕のその「想いを馳せる」行為には暴力性が潜む。
その暴力性に目を背けることをせずに、「不在」の者を「存在」させることを、「死者」の「声を聴く」ことを、めげずに時々続けていこうと思う。
それを続けた先に、何かが見えるだろうか。なにか「正解」がわかるだろうか。
確かなのは、死者の声を聴き続けても、僕はユタにはなれないだろう、ということだけだ。
(2)
最近、亡くなった祖父のことをふと思い出した。
祖父は学校の校長先生などをしていて厳格な人だった。らしい。僕にはあまり厳格だったとかはわからない。僕にはずっと優しかったし。
だからおじいちゃんは校長先生だったんだよーとかって言われても、「へぇー」くらいな感じだった。
僕が小学校低学年のとき、祖父母の家に遊びに行ったら、その日はなぜか祖母がいなかった。だいたいいつもいるのに。
僕が祖父母の家に遊びに行くときは、テレビゲームをするという目的があった。
家ではテレビゲームは(やんわりと)禁止されていて、だからどうしてもやりたいときは、友達の家か祖父母の家に上がりこんで何時間も熱中した。
その日、祖母が留守で、祖父は一人でいた。何をしていたか覚えていない。
僕がゲームの世界に嵌まり込んで、しばらく潜り続け、やっと現世に戻った時、祖父は僕に、「ご飯食べて行きなさい」と言った。
おそらく、祖父は、ご飯を作ったことがなかったんじゃないかと、いまは思っている。
でもそのときは「ご飯食べて行きなさい」と言った。「ご飯」は、カップラーメンだった。
カップラーメンを”作って”いる祖父の姿は、どこか心許なくて、うまくいかないのか少し苛立っているようにも映った。たぶんカップラーメンすら作ったことがなかったんじゃないかと思う。
そのときの、カップラーメンに四苦八苦しているときの祖父の後ろ姿を、僕は思い出したのだった。
なぜ、思い出したのは、あのときのカップラーメンの姿だったのか。
あの後ろ姿が、祖父との思い出として僕の中でもっとも色濃く残っている光景だったのだろうか。
そうかもしれない。改めて幼少期を思い返してみて、祖父との思い出として強く印象付けられてるものはあまり思い浮かばない。
なぜ、思い出したのか。
特に意味はないのかもしれない。脳のシナプスが誤作動を起こしてあの映像を引っ張り出してきのかもしれない。
でも、あの映像の中で立つ祖父の後ろ姿は、僕に何かを語りかけているように感じた。
教壇に立ち、組織の上に立ってきた教育者として。
たくさんの子どもたちを育てた父親として、あるいは幼い娘を亡くし、青年になった長兄に先立たれ、喪失を味わった父親として(僕の叔父や叔母にあたる人を亡くしている)。
少年時代に戦争の動乱に巻き込まれ家族を亡くした、戦争体験者として。
それ以外にもたくさんのことを経験し飲み込み咀嚼し消化してきた人間として。
複数の立場から、僕に何かを伝えようとしたのではないか、そう感じた。
生前、祖父から教育の話や家族の話や戦争の話を聞いた記憶はない。
そしてもう存在しない祖父から、直接それらのことを聞くことはできない。
でも、それでも祖父は「聞いてくれよ」と要請しているように感じた。
そして僕は、「聞きたい」と思った。いや、「聞かなきゃ」と思った。
祖父の声や言葉を受け取る義務を、僕は負ったのだと思った。もう存在しない祖父(死者)の声を、僕は受け取ったのだと思った。
死んだ人は、地面の下で、あるいは空の上から、ずっと声を発して続けているんじゃないだろうか。
誰に宛てるでもなく、でも誰かに届けようと、その声帯を振るわせ続けているのではないか。
でも地上にいる僕らは、その声に耳を塞ぎ続けてきたのではないか。
注意を向けようとしてこなかったのではないか。
この作品では、死者(?)の声は、なかなか届きません。
もしかしたら生きているかもしれませんが、それでもやはり届きません。
作中、死者(?)は饒舌に喋り続けていますが、それはだんだん寂しさを紛らわすためのものと思えてもきます。
目先の利益を優先して、あるいは目の前の生活にいっぱいいっぱいで、死者からの声は聞こえない。
でもそれは、仕方ないのかもしれない。生きている人間が、これからも生きていくためには、そうするしかないのだから。
でもたぶん、それくらいで死者は怒らないと思う。
祟りとかを引き起こすとか、そういうことはないと思う。
ただ、いつか聞き取ってくれることを願って、僕たちの「目の前」に向かって、その声を発し続けるだろう。
祖父母の家には、祖父の字で、教育者や哲学者などの言葉を引用した書が飾ってある。先だった子どもへの言葉が掛けられている。戦争体験を記した手記が保存されてある。
祖父が語ったこと。語らなかったこと。語りたかったこと。それらが、祖父母の家にはあちこち点在している。
それに最近、あまり婆ちゃんの顔も見ていない。
たまには、足を伸ばそうかと、この文章を書きながら考えている。
もう、テレビゲームはないけれど。