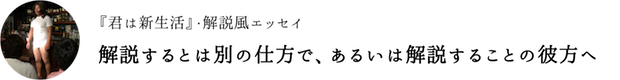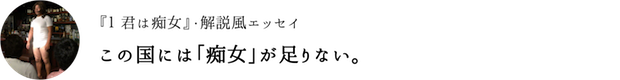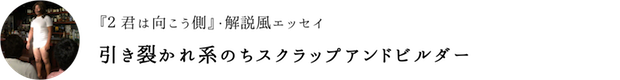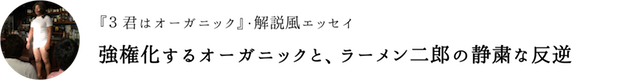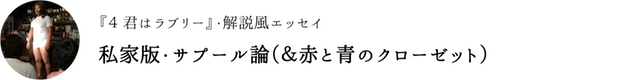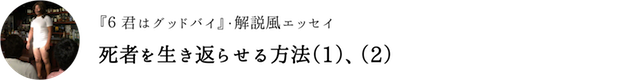私家版・サプール論(&赤と青のクローゼット)
『THE SAPEUR』(『サプール』と読む)という写真展に先日行ってきた。その感想を書く(解説はどうした!)。
アフリカのコンゴに、『サプール』という団体(?)があるそうです。
『サプール』とは、簡単に言えば「オシャレ集団」。
高級ブランドのスーツを身に纏い、シルクハットやステッキを携え、ヨーロッパ紳士の装いで街を闊歩する。それが『サプール』の活動である。
一口にコンゴと言っても《共和国》と《民主共和国》の二国が隣り合わせにあり、今回の写真展に関しては《共和国》の人たちが主ですが、《民主共和国》の方にも同じような『サプール』の習慣・コミュニティがあるようです。
どちらも鉱物資源が豊かでありながら、自らでその開発を進めることがなかなかできず、世界的にも最貧国のカテゴリーに属するといいます。
そんななかで『サプール』のメンバーは、一着の値段が月給の数倍もするようなスーツを購入したりすることも。
普通に考えると、その金額は生活費に回すのが賢明に思えます。
でもなぜ、彼らはそうせず、命を削るようなリスクを冒してまで、オシャレをしようとするのか。
そこには、「オシャレを楽しみたい」だとか「ファッションで自己表現をしたい」だとか、そういったこととは違う、もっと切実な動機があるように思うのです。
フランスの哲学者ロラン・バルトは論文の中で、「何世紀にもわたって、社会階級の数と同じ数の衣服が存在した」(「3 ダンディズムとモード」『ロランバルト・モード論集』)と述べた。
貴族には貴族の、平民には平民の服があった。「社会階級」と「衣服」との関連性はそれほど強く、「衣服を変えること、それは階級と人品を同時に変えることだった」(同)。
「何世紀にもわたって」続いていた「社会階級」と「衣服」とが強く結びついていた時代も、ある時から一気にその紐帯が緩んでしまう。というか、結び目が切り裂かれてしまう。
フランス革命である。
それ以降のフランスは(一応は)デモクラシーの観念に浸り、それは衣服の面でも適用された。
つまり、「みんな同じ服を着ていいよ」ってことになった。
女性服の場合は(現在でもそうだが)「構成要素(単位と言ってよいかもしれない)の数が多いので、まだしも豊かな組み合わせが可能」(同)だが、男性服の型はほとんど制服化してしまい、ブルジョアたちにとってそれは、それまであった自らの有利な立場を明確にしていた境界が溶けてしまうことを意味していた。だからこそ彼らは、その境界を「細部」によって引き直そうとしたのです(「服の生地」や「小物」や「着こなし方」など)。
「細部」の話に没入するともう抜け出せないので、しません。
表面上は民主化が進み、誰もが同じ衣服を着られるようになったフランス。
国内ではまあそんな感じでしたが、当然のことだが植民地でも同じようなことになっているかというと、そんなことはないはずで(予め記しておくと、ここから先は僕の独断です)。
コンゴ共和国は、一八八二年から一九六〇年に独立するまで、フランスの植民地であった。
フランスとコンゴ(共和国)の間には支配—-被支配の関係があり、そこでは生活水準の差も大きかったはずで、ってことは両者の衣服もまったく違ったものだったと思います。
さて、『サプール』です。『サプール』は、一九二二年、アンドレ・マツワというコンゴ人の社会運動家がフレンチファッションを身に纏ってパリから帰国し、そのスタイルに憧れた人たちの運動として始まったものであるらしい。つまり「マツワ、カッケーー!」となって「俺もやるー!」となって、『サプール』は生まれたのだ。
その運動の発芽は、マツワのファッションがセンセーショナルであったからなのか。それとも、マツワという人間に帰結されるものなのか。
Wikipediaを開いてみた。『アンドレ・マツワ』を調べると、その中にこんな記述があった。
マツワが設立した団体が黒人差別反対を訴え、彼自身も共産党大会に参加し、黒人の労働組合設立に協力した。
この記述から容易に看て取れるのは、被支配の立場からの「人種間の平等」あるいは「黒人の生活および地位の向上」をマツワが強く主張していたということである。
なぜ、マツワはコンゴに帰国した際、西欧紳士風の上質でスタイリッシュな服装をわざわざしていたのか。
彼が見栄っ張りだからだろうか?
恐らく、そうではない。彼のファッションには強い政治的文脈が読み取れる。
自国の地に足を踏み入れた瞬間から、「俺たちはいつまで支配され続けるのか?」という問いを、国民に向けて突きつけたのだ。「平等の旗を掲げろ!」と煽り立てたのだ。
そして彼がコンゴ人に配った武器が、銃器や爆弾ではなく、「衣服」だったのだ。
『サプール』の人々は、自らのファッションを「非暴力」や「平和」と結びつけて語る。
ここで言う「非暴力」や「平和」という言葉は、インドにおいてガンジーがやったようなものと同じ文脈で語られているものだ。
「平等」を実現するために「衣服」を用いるのだという意志がここにはある。
彼のスタイリッシュな衣服と、それに包まれた「平等」あるいは「生活および地位の向上」を求める姿勢。
それにコンゴの人間たちは羨望を抱き、『サプール』という運動にコミットしていったのである。
この「平等と権利獲得への意志と姿勢」を身に纏った人々の発する熱が、一九六〇年に成就するフランスからの独立へと繋がっていったのではないだろうか。
面白いのは、マツワのスタイリングが、支配国であり仮想敵であるはずのフランスのそれだったということだ。
それは一見、おフランスにカブれてるようにも、支配者に魂を売ったようにも映るのではないだろうか。
でもそこにも、マツワの思想が反映されている。天理大学の森洋明いわく「彼は単なる反植民地主義者ではなかったようだ。(略)彼の願う黒人の生活向上は、白人の『知識』を習得していくことによって成し遂げられると思っていたようである」(『アンドレ・マツワの生涯と黒人メシア宗教の誕生』)。
「俺たちの地位を上げろー!生活水準を上げろー!」とただ声を発するのではなくて、「俺たちこそちゃんと、その地位にふさわしい知識とか教養とか身につけようぜ」と言っているのである。
その「知識や教養」の一つとして「ファッションセンス」というものを捉えていたのではないだろうか。
この「ファッションセンス」こそが、自分たちの生活水準を変革させ得る装置として鍵を握ることになる。
それはファッションデザイナーの森永邦彦が語る「洋服は唯一残された日常を変える手段」(『情熱大陸』2014.10.12放送)という言葉を、貧国での生活というまた違った文脈において語り直すことである。
衣服は、フランスでもかつてそのように機能していたように、自らの社会階層を示す記号としての働きを持つ。
『アルマーニ』のスーツと『しまむら』で買ったセットアップでは、その使用価値は等しい(どちらも身体を隠す、保護するという機能を持つ)が、両者が象徴する価値は全く異なる。どっちがほしい?と聞かれればほぼほぼアルマーニだ。
『サプール』のメンバーが分不相応に高級なスーツに身を包むことには、社会階層の上昇あるいは生活の向上を目的とした「投資」の意図があるのではないか。
それは彼ら自身がというよりも、子ども世代・孫世代によって達成することまでも見越したものだ。
普通、上昇のための「投資」と考えるなら、「新規事業」や「教育」という面でのそれを連想する。
「新規事業」という投資活動について考えてみる。
アフリカ大陸に存する貧国においては、国民の暮らしのほとんどが地下経済によって営まれているという。
つまり僕たち日本人が「働く」というと真っ先にイメージされる「サラリーマン」みたいな存在が、このような国では逆にマイナーな存在なのだ。
それよりも露天商などの「その日暮らし」の人が圧倒的に多い。
文化人類学者の小川さやかが言うように、地下経済従事者たちが置かれた立場は、彼ら自身の事業アイデア等について「計画を立ててもどうにもならないような状況に置かれている」(『「その日暮らし」の人類学』)。
露天商などの地下経済が主流の地域では、「儲かる商品」に商人が殺到し、競争が激しくなり、結果的に事業を営むのが難しくなっていく。
だから彼らはリスクヘッジとして複数の専門性を持ったり、個人・世帯単位で生計の多様化を図ったりする傾向にある。
そういった状況においては「計画的に資金を貯めたり、知識や技能を高めていく姿勢そのものが非合理、ときには危険ですらある」(同)。
さらに、コンゴの平均寿命は約五八歳で、日本と比べると二〇歳ほど低い。だからそこに住む若者にとって「『老後』は備えるものではなく、無事に到来することを祈るものである」(同)。
投資回収までにかかる時間が長くなればなるほど、損失の可能性も高まってしまうのは当然だが、コンゴのような国ではよりそのリスクが高まる。ごく短い期間でリターンが減ってしまったり、あるいはまったくの水泡に帰すこともあり得る。
今度は「教育」という側面で見てみる。
教育とは本来的に、日本や韓国などで見られるような受験と教育がイコールで結ばれるような競争主義的なものではなく、そのアウトカムが一〇年〜二〇年後に出てくるのであり、そのような長期的な視座に立って捉えなければならないものである。
「世界子供白書2013」によると、二〇〇八〜二〇一一年におけるコンゴの初等教育の純就学率は、男性九二%、女性八九%(出席率は男性八六%、女性八七%)。それが中等教育になると出席率は男性三九%、女性四〇%となる(就学率はデータなし)。
中等教育になると数値が下がるのは、先ほども述べたように世帯内での複数生計を図るため、初等教育終了時点で労働の担い手としての役割を引き受けるからだろう。
教育にかける時間的・金銭的「投資」は、切羽詰まった家計状況のためにゆっくりと利食いしていくことはできず、すぐに払戻しを行わざるを得ない。
このようにコンゴにおける「新規事業」や「教育」という「投資」活動は、リスクが高いにもかかわらずリターンが高いとは言い切れない部分がある。
ではなぜ「衣服」なのか。
それを考えるためには「文化資本」という概念を補助線として引っ張る必要がある。
「文化資本」とは、フランスの社会学者ピエール・ブルデューが提唱した概念である。
彼はこれを用いて社会階層の理論を構築した。「資本」といってもお金のことではない。というか「資本」とはもともと「お金」のことではない。
「資本」とは「剰余価値を生むことによって自己増殖を行う価値の運動体」のことである……
ううむ。わからない。なのでざっくりやっちゃうと、つまり「利潤をうみだすもの」のことを言う。
だから「文化資本」とは、「利潤をうみだし得る文化的素養」つまり「知識や教養」のことをいう。
ブルデューが暴いたのは、「文化資本」の所有の格差によって階層が分断されている、という現代社会の現実だった。
経済的格差があるところでは、ほとんど文化資本の格差も伴う。というよりもむしろ、社会の流動生を滞らせてしまうものは、経済資本の格差よりも文化資本の格差の方がその濃度が高い。
「『文化資本』が作る境界線と、『年収』が作る境界線とでは、『壁』の厚さも高さも桁が違う。年収は本人の努力でいくらでも変わりうるけれど、子供の頃から浴びてきた文化資本の差は、二〇歳すぎてからは埋めることが絶望的に困難だからである」(内田樹『街場の現代思想』)。
「文化資本」にも種類があり、「生まれ育っているうちに自然に身についてしまったもの」(身体化された文化資本)と、後天的に努力によって身につけたもの」(制度化された文化資本)と分けることができる。
前者は、主に「家庭」等において獲得された趣味やマナーや教養を指し、後者は「学校」等において学習された知識・技能・感性などを指す。
「親の仕事の影響で小さい頃から海外を転々としてたので4ヶ国語しゃべれるんです」みたいなのは前者で、「勉強を頑張って難関国立大学に合格しました」は後者といえる。
そのなかでも特に、ブルデューは「身体化された文化資本」に注目する。
高いレベルの文化教養を幼い頃から浴びるように享受してきた貴族の子どもは、「なんか良い」と選んだ事物が、洗練されていたりする。つまり「センス」が良い。
その「センス」の良さと階層とが比例している現状が凝り固まってしまったのが現代社会なのだ。
『サプール』の人々が語るように、彼らのファッションおよび活動は「平和」や「非暴力」とコミットする。
その思想が重要であることは疑いようがないが、さらに重要なのは、衣服が衣服であること、つまり衣服の物質性である。
『サプール』においてはその精神的継承と同じくらい、いやそれ以上に、衣服そのものの物質的継承が重要なのだ。
幼い頃から、スマートな着こなしやビビッドなカラーリングのコーディネートを身近で浴び続けていることで、ファッションセンスは身につく。つまり「文化資本」が身体化されていく。
高級(質)な衣服を継承していくことで、将来の世代において、社会的上昇を果たす子孫が生まれるかもしれない。
その物質を所有し続けている限り、その可能性は常に存在する。
だからこそ彼らは、その不安定な生計を削ってまでも衣服への投資を行うのではないだろうか。
さて、『サプール』の話があまりにも長くなってしまった。これから『君はラブリー』の解説をほんのちょっとだけ書く。「いまさら感」も甚だしい。
現代の日本においては、衣服が「階級を示すための記号」としての機能を果たしているとはいえないだろう。
まあたしかにハイブランドのものをジャラジャラと飾り付けている人も時々いるけど、それは「金があって趣味が悪い」というようにも捉えられる。
バルトが考察したみたいに、細部のちがいがセンスの良し悪しを左右するのである。その細部を互いに暗黙のうちに察知しあうセンサーの働きが、現代日本の「オシャレ(あるいは「カワイイ〜」)」をつくっている。
僕は今ここで偉そうにファッションやオシャレについて語ってはいるが、正直それ自体にはあまり興味がない。大事なのは「モテそうか、否か」だったりする。
「モテる格好」という正解が予め決まっていれば困難はないが、問題はその答え(でありそうなもの)が常に複数存在し、しかもそれらは瞬く間に別の解へと形を変えていく。
だから僕のような人間は、ファッション(衣服)自体への興味はそれほどないにもかかわらず、それらへの消費欲だけはいつまでたっても静止することがない。そのパラドックスに苛まれながらも、今年のトレンドをやんわりと取り込んでいく。
この短編のタイトルは『君はラブリー』であるが、「ラブリー」というと「愛らしい」みたいな意味合いで使う言葉かと思う。
つまり「モテ」だ。
女性が、モテそう(好感を持たれそう)な衣服を着用するのが、僕の稚拙なファッション知識を適用すると「赤文字系」とでも呼ぶべきものだろうか。「ふんわり」していたり「キレイめ」だったり、ラブリーな装いは男性からの好感を獲得しやすい。
逆に「青文字系」は、自分の個性や感性を優先させた、表現色のつよいファッションのことをいう(のでよいのかな?)。自らのアイデンティティを衣服によって発露させたその姿勢は、異性よりむしろ同性に(つまり女性に)好まれる傾向が強いように思う。
作品上で、人形には「ラブリー」を、死んだ彼女には「アイデンティティ」をそれぞれ着せ、あえてはっきりと区別している。
でも実際のところは、いまはその「赤文字系」と「青文字系」の境界部分は随分曖昧になっているものかと思う。
CanCamのような雑誌でもドラスティックな要素が入り込むこともあるだろうし、服のスタイル関係なく若い女性はみんな前髪を「オン眉」をしている気がする(偏見だと認める)。
つまり、「赤文字系」「青文字系」というその言葉や傾向自体がもはや形骸化している可能性もある。まあ、実際そこのところはよくわからないが(先ほどから語尾がすべて「憶測」であることに気付いているだろうか)。
でもあえて対立させたのは、クローゼットから服を取り出した瞬間に政治的なスイッチが押される、ということを浮き彫りにしたかったからだ。
中心に「権力」というものを仮置き、そこから距離をとって自主性・自律性を獲得するのか。あるいは、「権力」と友好なコミュニケーションを築いていくか。
自己利益の最大化をめざす両方の戦略を前景化させようと思った。
どちらの戦略が優れているかとか、倫理道徳的にどうだとか、そういったことは全然わからない。というかどうでもいい。そのときどきに合わせて選択すればいいだけの話だ。
僕らが着る服を選ぶときも、たぶん無意識にそうしている。そのことを、一応自覚しておこう、というのが、この作品の主題である。